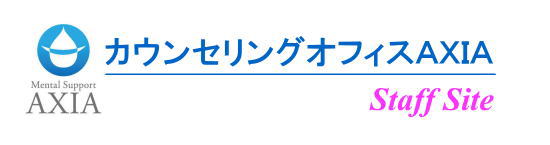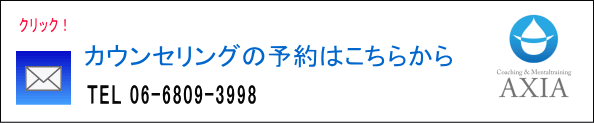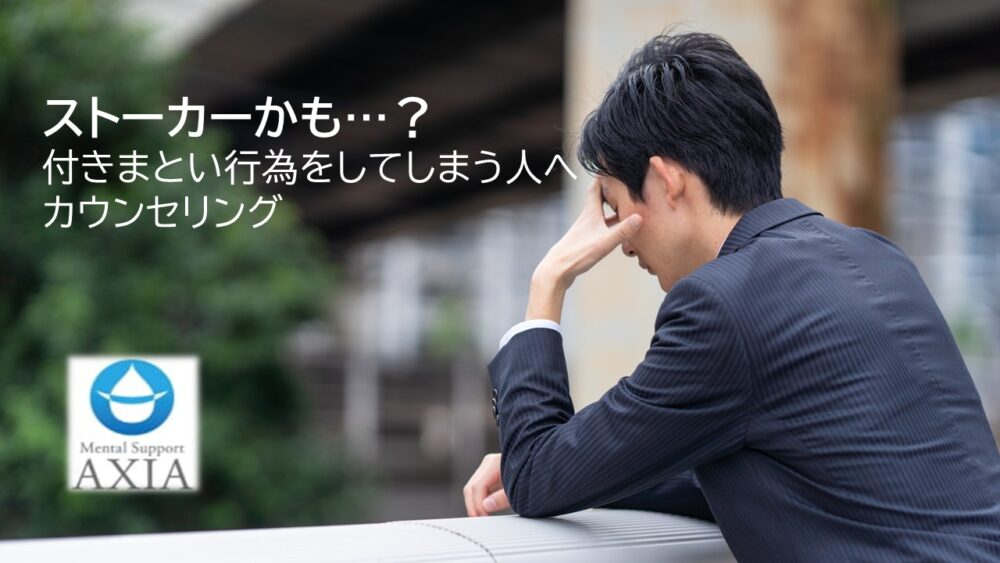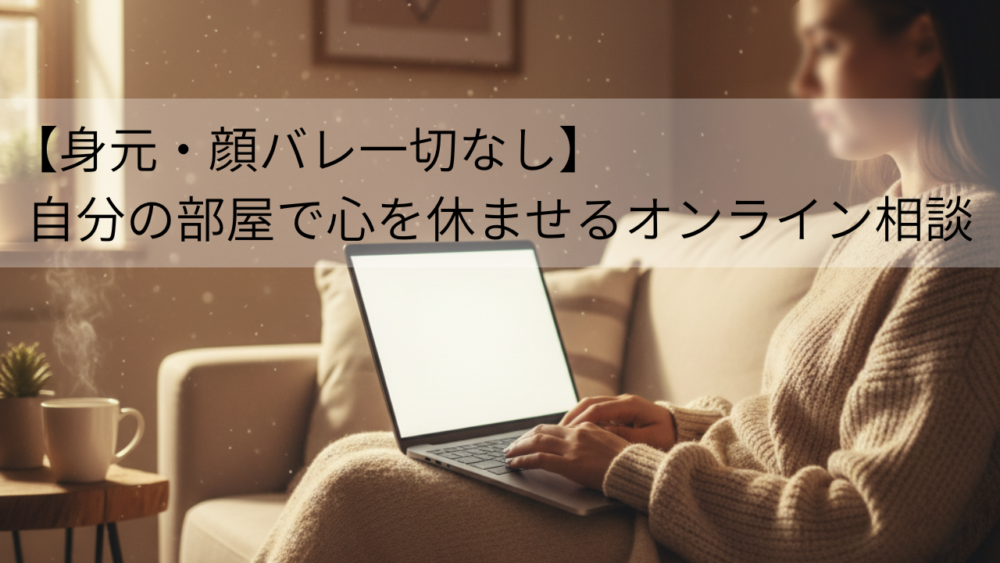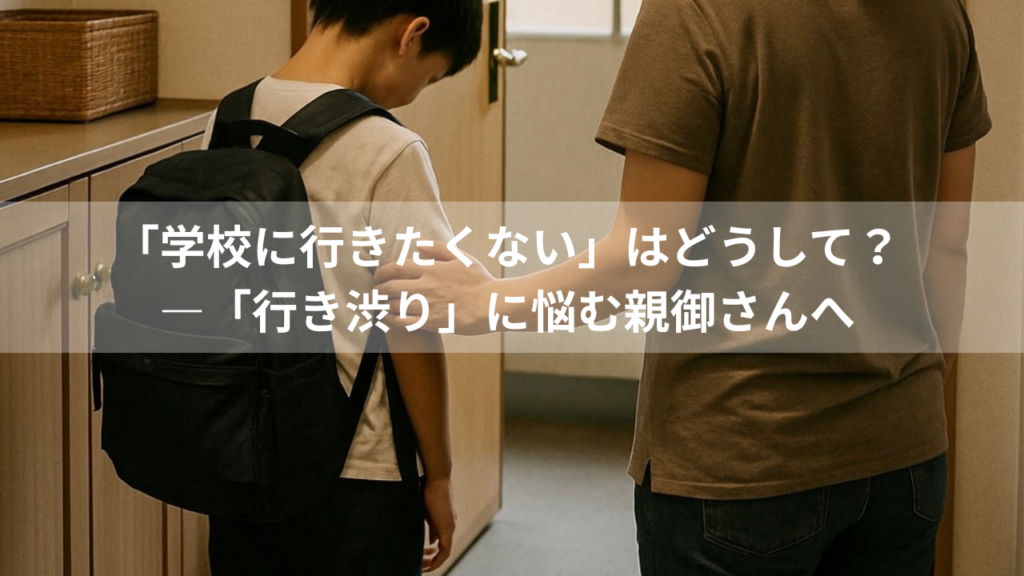
子どもが「学校に行きたくない」と言うと、親としては心配でたまりませんよね。
毎朝の登校時間になるとぐずったり、泣いたり、場合によっては体調不良を訴えたり…。
でも、完全に不登校というほどでもなく、行ける日もあれば行けない日もある、そんな状態が続く。
これを「行き渋り」と呼びます。
◆行き渋りの背景にはどんな気持ちがあるの?
子どもが学校に行きたくなくなる理由はさまざまです。
例えば、
- いじめではないがクラスの人間関係で嫌なことがある
- 授業や課題が難しく感じて自信がなくなっている
- 先生や友だちとのコミュニケーションに不安がある
- 家庭での問題や環境の変化に戸惑っていて行く気にならない
こうした気持ちが積み重なると、学校へ向かう心のエネルギーが不足してしまいます。
体調が悪いわけではないのに「お腹が痛い」と訴えるのは、心の不安やストレスが体に現れているサインです。
親御さんとしては、「早く行きなさい」と言いたくなりますが、無理に行かせることで子どもの不安が強まってしまうこともあります。
逆に放置すると、ますます登校が難しくなってしまう…そのバランスがとても難しいのです。
◆親御さんがやりがちなこととその影響
よくあるのが、
・「みんな行ってるよ」と責めてしまう
子どもは”個性”が確立していく成長の途中段階にあります。
”みんなと違う=いけないこと”という認識を受け付けてしまうのは好ましくありません。
ここで大事なのは、子どもの視点に寄り添い、「みんなと一緒のようにはできない」と感じていることへの背景を知っていくことです。
・「私だって仕事しんどいんだから、わがまま言わないで」
普段から「いい子にできる?」と声掛けをするご家庭も多いかもしれません。
それ自体が悪いと言うのではありませんが、その関わりによって子どもは迷惑をかけてはいけないと感じることも…。
言葉にしなくとも疲れた表情やため息などから、子どもに伝わっている可能性もあります。
考えの前提を見直し整理する必要があります。
・「行ったらお小遣い/お菓子あげるよ」と報酬でコントロールする
思考回路が比較的に単純な動物にとっては、報酬と罰は効果的かもしれません。
人間も動物ですが複雑な思考や感情が備わっている生き物です。
コントロールへの反発心や、嘘をついたり欺いてより楽に報酬を得ようとするのも人間の心理です。
お小遣いやお菓子を与える教育は、親が楽をしているだけの可能性もあります。
こうした対応は手っ取り早く問題が解決したように見えても一時的や表面的であることが多いです。
子どもは「自分の気持ちは理解されていない」と感じたり、「考えるよりも親の言うことを聞いていた方が楽」と思うかもしれません。
この傾向は、今後の親子関係や子どもの心の問題をさらに悪化させてしまう可能性が大いにあります。
褒めることやご褒美をあげることも大事ですが、根底になる問題を無視して与える報酬はリスクもあるのです。
◆じゃあ、どうすればいいの?
まずは、子どもの気持ちに寄り添いましょう。
無理に「どうして?」と詰め寄るのではなく、「つらいんだね」「行くのが怖いんだね」と言葉にしてあげることが大切です。
理由や考えを聞き出そうにも子ども自身が自分の複雑な気持ちを整理できていないことがほとんどです。
子どもが自分の気持ちをゆっくり整理し言葉にしていけるよう、話しやすくなる環境を作ってあげてください。
また、親御さん自身も抱える不安や焦りを少し横に置いて、子どものペースを尊重することが必要です。
毎日学校に行くことが理想ですが、今日無理なら明日、少しでも学校に向かう気持ちを支えてあげるスタンスが有効です。
◆カウンセリングがどう役立つの?
子どもが行き渋りを続ける背景には、子ども本人だけでなく、親御さんの心の疲れや家族のコミュニケーションの困難さが関係している場合がほとんどです。
カウンセリングは、そんな家族の悩みを整理し、問題の本当の原因にアプローチするお手伝いをします。
- 子どもの不安やストレスの正体を一緒に探る
- 親御さんが感じる不安やイライラの整理をサポート
- 家族みんなが安心して話せる場を作っていく
- 家庭での接し方や関わり方を具体的にアドバイス
これらを通じて、少しずつ心のバランスを取り戻していけるのがカウンセリングの良さです。
◆最後に
子育てに正解はなく、当然ですが完璧な親は存在しません。
大切なのは「一緒に悩み、考える姿勢」です。
少しずつでいいので、子どもが一人の人間として安心して過ごせる居場所を一緒につくっていきましょう。
カウンセリングは特別なことではなく、誰にでも必要な時がある心のメンテナンス。
行き渋りで悩む今こそ、プロに話を聞いてもらい、家族がよりよい方向に進むためのステップとして利用してみてください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓