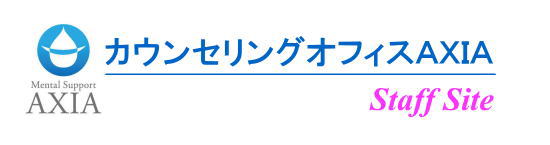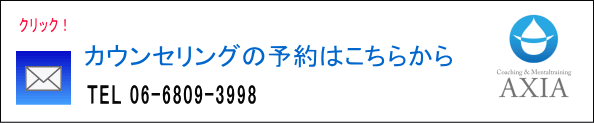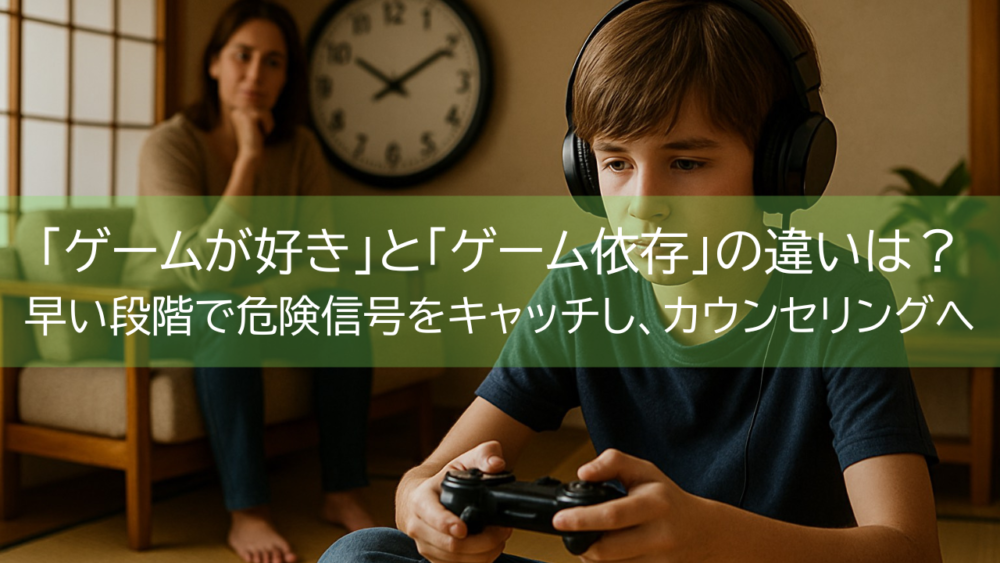「依存症って薬物治療でしか治らないんじゃないの?」
そう思われる方もおられるかもしれません。
しかし、適切にカウンセリングを行えば改善していきます。
依存を取り払っていくためには、依存の背景を知ることが大切です。
依存についてどんなものがあるのか掘り下げていきましょう。
さまざまな依存症
”依存症”と聞くとどんなものを想像しますか?
薬物やアルコール、タバコなど体に取り入れる物質的なものを想像する方が多いのではないでしょうか。
身体に害があるものや中毒性があるというイメージは根強いと思われます。
もちろんそれらは代表的な依存症ですが、他にも依存症はあります。
依存の対象別に大きく3つに分類しました。
◆物質に依存
前述したような、
- 薬物
- アルコール
- タバコ
- カフェイン
など、物質に中毒性があり依存してしまうものです。
アルコールやカフェインなどは適量でしたら人体に害はほとんどありません。
最初は趣味の1杯程度の晩酌が、次第にストレス発散目的となり制御が出来なくなっていくこともあります。
カフェインも集中したいときに飲んでリラックスできていたのが、次第に飲まなくてはひどい眠気やイライラの原因となり私生活に影響を与えます。
◆行為に依存
これは行為そのものに依存してしまうものです。
- ギャンブル賭博
- 窃盗、万引き(クレプト)
- セックス依存
- 買い物依存、浪費癖
- 摂食障害
- 自傷行為(リストカット等)
などです。
「高級ブランド店で買い物をした時、いつもとは違う特別な対応をされ自分がセレブになったように感じた。
さらに帰り道では高級ブランドのショッパーを持っているせいか注目を浴びているように感じ、優越感があった」
「なんとなく始めた出会い系アプリでたくさんのアプローチを受け、嬉しい気持ちになった。
求められるがままに性的な関係を持ち、自分は必要とされる存在なんだと感じられた」
など、最初は些細なことがきっかけでも一時的に”心が満たされた出来事”として脳に記憶されます。
そして、心が不安定になる度にその出来事を脳が思い出し、再び経験しようとするのが依存症の始まりです。
◆人に依存
人物やその人との関係に依存している状態です。
- DVされているが離れられない
- 恋愛依存症
- ホスト依存
- 人への依存
など、否定されたり支配されたり、いないと不安になったり苦しい関係性にあります。
人への依存は共依存である場合が多く、依存対象の相手も物質・行為・人に依存していることもしばしばあります。
「パートナーがアルコール依存で生活が心配で、自分がパートナーの身の回りの世話をしている」
「自由がないほど束縛されているが、自分もパートナーがいないと不安で仕方がない」などのケースです。
このように依存対象が物質・行為・人のように分類することが出来ます。
依存症になる脳の仕組み
依存症は脳の「報酬系」という神経回路と深く関係しています。
その名の通り報酬である物質の摂取や行為をすることで、この神経回路が働き、快楽や一時的な安心感を得るのです。
一時的には、不安な気持ちから解放されます。
しかし一定時間後には罪悪感や自尊心の低下が繰り返し訪れます。
こうして繰り返されることで依存行為が加速します。
これを繰り返すことで、脳が物質または行為と快楽を結び付けて記憶し、徐々に依存に繋がっていくという仕組みです。
そして、どの依存タイプにも共通して言える依存の背景や依存しやすい人の特徴があります。
依存しやすい人の特徴
上記に挙げたそれぞれの依存は内容こそ大きく違いますが、心理的な背景は共通点があります。
依存症になりやすい人は
- 自己評価が低い
- 自分で考えようとせず、流されやすい
- 寂しがりで見捨てられる不安が強い
- 本音を言えないもしくは分からない
- 自分を大切に出来ずリスク管理が苦手
という点が共通して見られます。
自分に自信がなく流されやすい人は、他人から自尊心を満たそうとします。
例えば、「恋人から毎日尽くされないと気持ちが不安定になる」や、
「ホストである彼の夢を応援することが自分の生きがいになる」などです。
自分のメンタルや自分の生きがいを相手に委ねることになってしまいます。
これが進行すると、どんどん自己評価が低くなり抜け出せなくなります。
依存症の方へのカウンセリング
当カウンセリングルームは依存症で悩んでいる方へのカウンセリングを行っています。
また、意志を強くすることやペナルティを課すなどの対処を思い浮かべる方もおられるかと思います。
ペナルティを課すことは一時的には効果があるかもしれませんが、根本的な要因には向き合えていません。
そのため、依存対象や依存の種類を変えて繰り返してしまいます。
まずは、依存行為の背景に焦点を当てることが重要になります。
育った環境やこれまでの体験に基づき話してもらい、どういった経緯で依存するようになったのかを明らかにします。
つまり、カウンセリングでは意思を強くするのではなく依存していた自己の分析をしていく作業になります。
その上で依存せずともいい自分や環境作りをし、持続することを目指すサポートをさせていただきます。
「薬でしか治らない」「依存症は治らない」そう思われていた方もまずは、一度ご相談ください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓