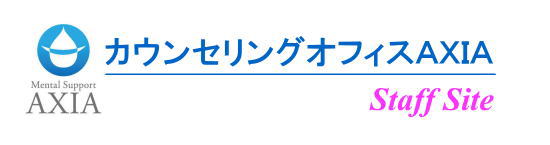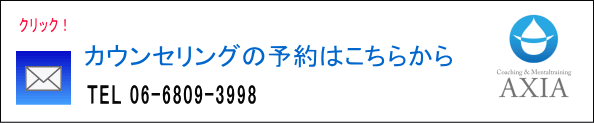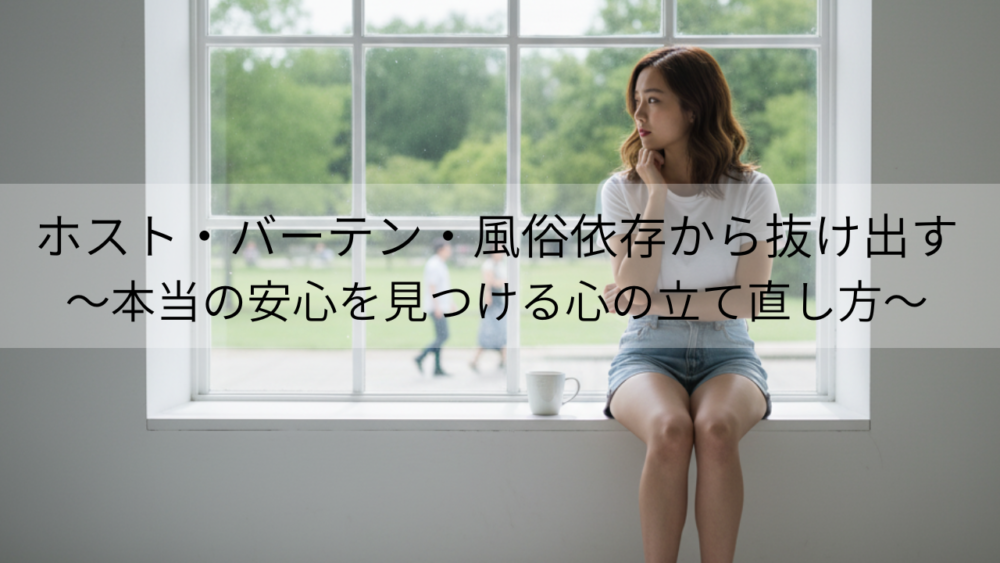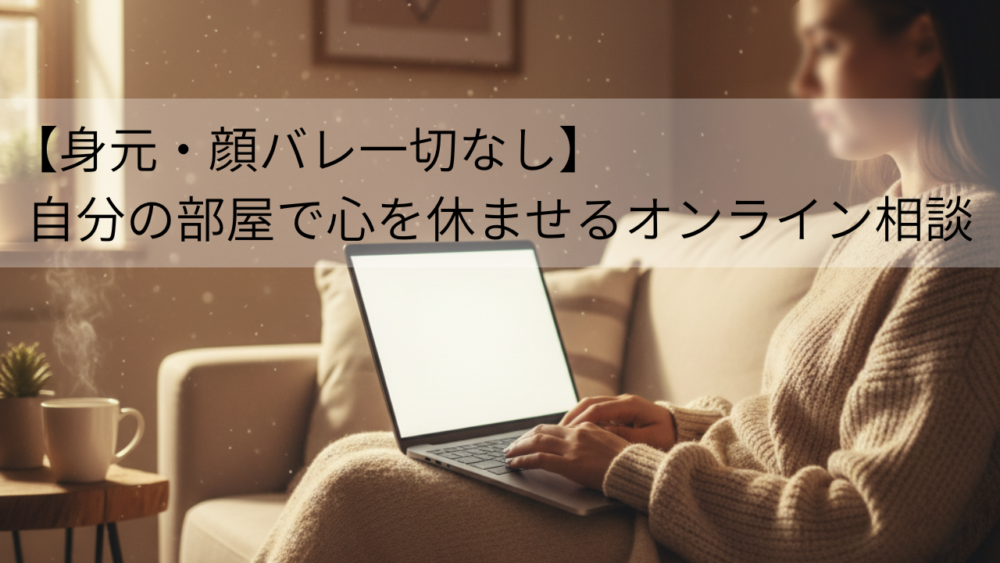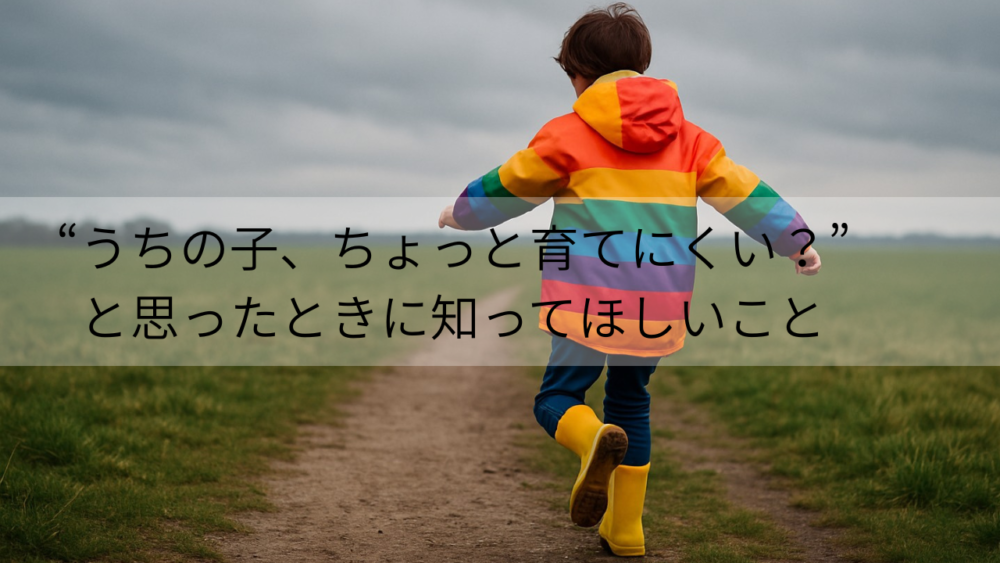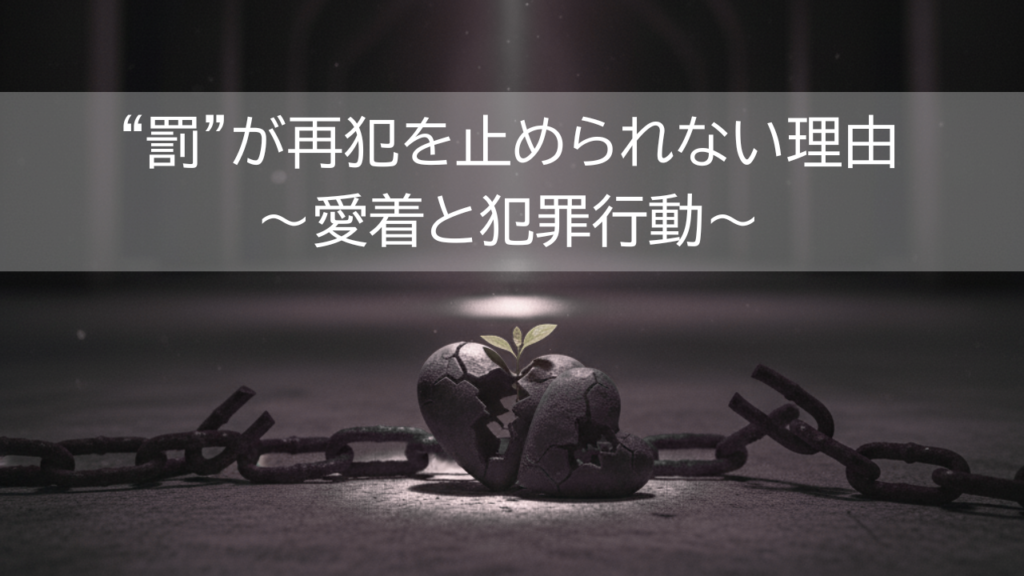
盗撮行為や痴漢行為、万引き行為など依存性の高い犯罪行為はほとんどの確率で再犯します。
刑罰を受けても再犯してしまうのはなぜなのかを、お話していきたいと思います。
罰は再犯防止には直結しない
犯罪加害者には法律で裁かれ”罰”が与えられます。
もちろん身勝手な理由で人を傷つけた行為には、罰が与えられるのは当然のことです。
多くの人は罰によるリスクを恐れ、その恐怖が犯罪行為の抑止になっているのも事実です。
罰がなければもっと多くの犯罪加害者が存在し、その倍以上の被害者が生まれることでしょう。
しかし再犯抑止という観点では、罰による効果はそれほどありません。
その理由についてこれからいくつか説明いたします。
犯罪を犯す人としない人の違い
身勝手な理由で罪のない人を傷つけるような犯罪行為をする人は、しない人と比べて格段に相違する点があります。
その一つは、共感力です。
犯罪行為の抑止につながる能力の一つである共感力が欠如しているのです。
人の気持ちや他人からの視点を頭で理解はできても、解像度の高いイメージにすることが困難な方が多いのです。
共感力が高い人は自然と「自分がされたらどう思うだろう」と考えることが出来ます。
また、他人からの視点を想像することで「こんなことをしている自分は嫌だなあ」と自分自身のために不適切な行為を止めることが出来ます。
犯罪を繰り返してしまう人は、自分のしたことが悪いことだと理解は出来ても、リアルな共感的なイメージがしづらいのです。
その要因の一つとして、育ってきた環境が挙げられます。
共感力には愛着の形成が影響している?
幼い頃、親から注意されてしまった経験がおありかと思います。
子どもは善悪の判断が出来ないため、意図せずに望ましくない行動を起こしてしまうものです。
そんな時、親が子に罰として強く叱責し暴力で躾ける、もしくは無視したり家の外に出すなどの関わりをすると、子は理解できず反感や葛藤を抱きやすくなります。
一方で、望ましくない行動をした理由を聞き、子の意図や気持ちを理解するように接しながら子が理解できる言葉を使って間違った行動について説明する関わりをすれば、共感力は自然と高まっていきます。
つまり、暴力や恐怖による罰や、突き放されるような関わりを受けて育った人の方が、共感力が乏しく道徳的な価値観が備わりにくいとされています。
愛着の不安定さと犯罪行動の関連
これまで当カウンセリングオフィスでも愛着に関する記事を掲載してきました。
愛着が不安定に育った人は、
-
-
-
-
-
- 共感力や想像力
- 社会性の発達
- 葛藤の処理能力
- 感情や行動のコントロール力
などが、低い傾向にあります。
-
-
それらが低いことで、
「相手も嫌がっていないと思った」
「バレないと思った」や「バレなければセーフ」、
「ストレスがあったし性欲を抑えられなかった」
「逮捕されて初めて家族や仕事を失うことへの恐怖を感じた」などの気持ちや考えに至りやすくなります。心理学者のKochanska & Kimらの研究でも、愛着の不安定さが犯罪行為の抑止を妨げ犯罪行為を促進していることが述べられています。
この考えの修正を日常性価値や過去を振り返りながら行うのが、再犯防止の第一歩です。再犯防止のためのカウンセリング
当カウンセリングオフィスでは再犯防止のためのカウンセリングを行っています。
罰だけでは再犯防止には繋がらないのです。その犯罪行動に至った背景を解明し、考え方の癖から修正していくため継続的なカウンセリングが必要です。
罰が犯罪の抑止になっていることは間違いありません。
しかし、罰だけでは再犯防止という点では不充分なのです。再犯防止に必要なことは、罰よりも自己を理解することです。
叱責や社会的なバッシングではなく、なぜ犯罪行為をしたのかやその背景にある気持ちを探ることが必要です。
愛着の不安定さや共感力の欠如に気づき、自身が納得いく言葉や方法で自己理解を深め、共感力を養うことが再犯防止に繋がります。カウンセリングでは、共感的理解をしながら犯罪行為の背景を探っていくサポートをさせていただきます。
犯罪を犯してしまった方、もしくはしてしまうのではないかとと不安な方はまずはご相談ください。
ご家族の方や周囲の方もご相談いただけますので一度お問い合わせください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓
-
-