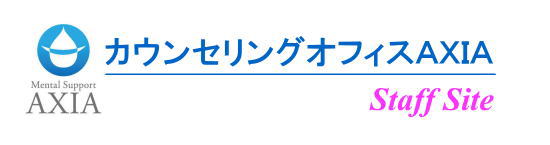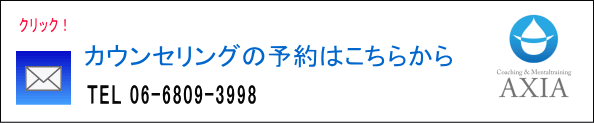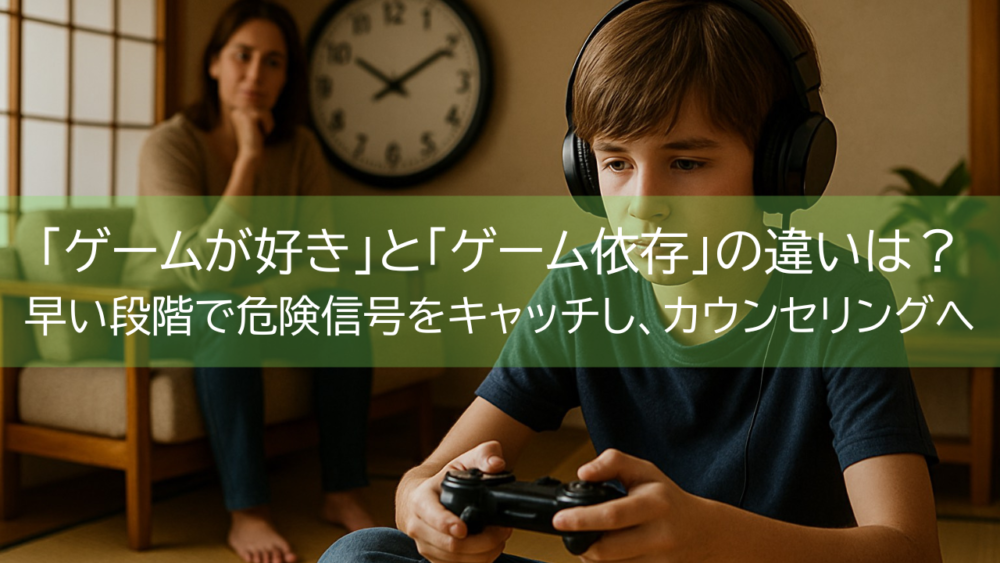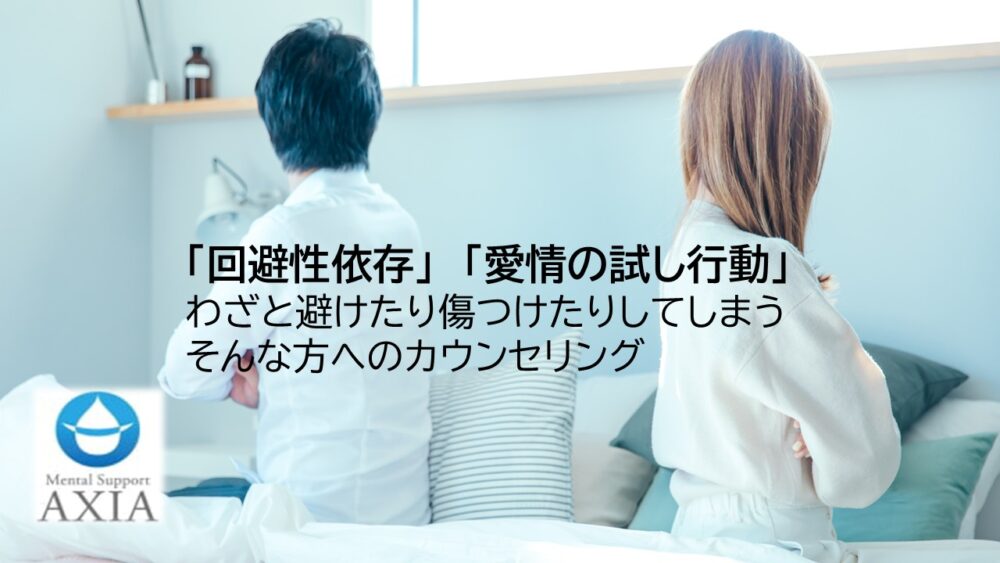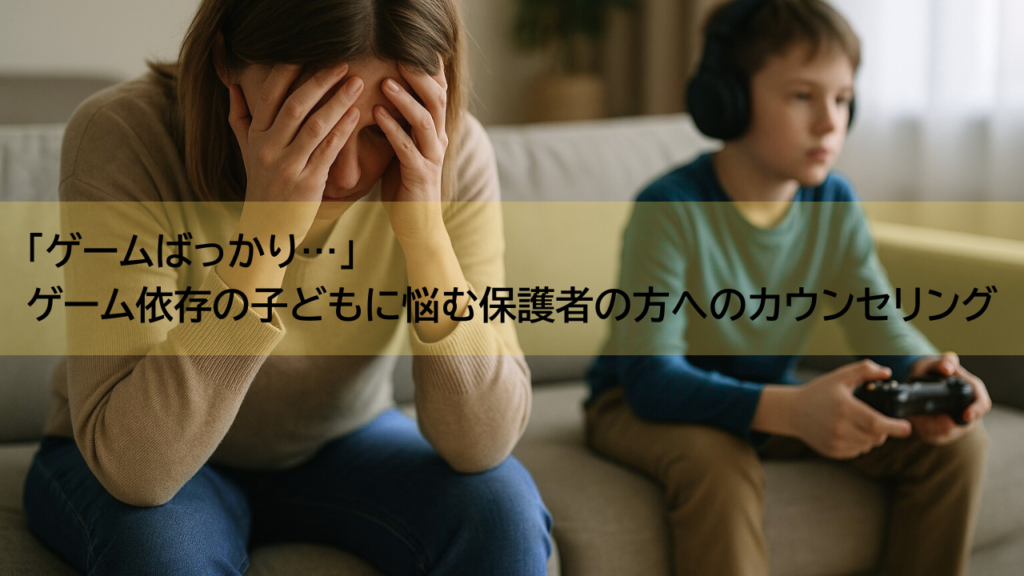
~叱るだけでは変わらない、親ができる本質的な関わり方~
◆「うちの子、ずっとゲームばかり…」その背景には理由がある
「気づけば何時間もゲームをしている」
「話しかけても無視。ごはんにも来ない」
「取り上げると暴れる、無気力になる」
こうした悩みは、今や珍しいものではありません。
実際、私のもとにも「ゲームをやめさせたい」「生活が乱れてしまって困っている」という相談が多く寄せられます。
ここで一つ知っておいてほしいのは、子どもがゲームにのめり込むのには、必ず理由があるということです。
もともとの性格や暇つぶしや楽しさだけでなく、現実のストレスや孤独感、自分に自信が持てない気持ちから「逃げ場」としてゲームに依存していくことがほとんどです。
◆「ゲームを取り上げる=解決」ではない
多くの親御さんが最初にするのが、「ゲームを禁止する」「ペナルティを課す」といった対応です。
しかし残念ながら、それでうまくいくことはほとんどありません。
逆に、
- より怒りっぽくなる
- 家族との会話がなくなる
- 学校や外との繋がりも絶たれていく
といった悪循環に入るケースが多く見られています。
子どもの問題行動を“力で抑え込む”やり方では、一時的に止まったとしても根本の問題は解決しません。
ゲーム依存とはまた違う不適切な行動(万引きやSNSトラブル)にうつるケースがほとんどです。
大切なのは、なぜそこまでゲームに依存しているのかを捉え、家庭の関わり方自体を見直していくことです。
◆ 感情に振り回されない「対応力」が鍵
「またゲームしてる…」「いい加減にしなさい!」
と、つい怒ってしまうのは当然です。
でも、怒りは多くの場合、子どもとの距離を広げるだけになります。
「私の育て方が良くなかったのか…」「どこで間違ったのだろうか…」
と自分を責めてしまい、なぜ普通に育ってくれないのかとストレスを溜めていってしまいます。
それは”間違った”ではなく”掛け違った”んです。
掛け違いを直していくように、関わりを変えていく必要があります。
カウンセリングでは、そんな掛け違いに気づいていくことを大切にしています。
- 自分の言葉や態度が、子どもにどう影響しているか
- 子との関わりで困った時にどうしているのか
- どんな時に怒ってしまい、何がきっかけで感情が爆発するのか
- ゲームに対して「どんなイメージ」や「期待・恐れ」があるのか
つまり、「子どもをどうにかする」のではなく、親自身の関わり方のパターンに気づき、整えていくことが最初のステップになります。
◆ カウンセリングで一緒に進める「関係の立て直し」
私たちカウンセラーが行うのは、一般的なアドバイスではありません。
ひとつひとつの家庭の状況を細かく聞きながら、
- 親子のコミュニケーションパターン
- 家庭内でのルールや個人間の境界線のあり方
- 子どもの「本音」がどこにあるか
を見立て、具体的な対応方法を一緒に整理していきます。
”掛け違い”をひとつひとつ見つめ直していくことで例えばこんな変化が実際に起きています。
- 母親自身がイライラや無力感から解放され、家で安心感を取り戻せた
- 今までは「うるさい!」と怒鳴っていた息子が、母親の言葉を少しずつ受け入れるようになった
- 1日中ゲームにこもっていた子が、自分から学校の話をするようになった
認識や頑張る方向性を変えることで、親子間のコミュニケーションも変化し、子どもの行動も変わっていくという結果です。
◆ こういう方にこそカウンセリングをおすすめします
「どれだけ叱っても何も変わらない」
「家族の雰囲気がギスギスしている」
「夫と意見が合わず孤立している」
「子どもの将来が不安で仕方がない」
「冷静で建設的な対話をしたいと思っている」
このような状況だとストレスを一人で抱え込み、それがまた子どもとの接し方に出てしまい悪循環になります。
その悪循環を断ち切るためにもまずは自身の考えや方向性の整理をしておきましょう。
◆最後に:親もまた「回復の当事者」
子どもの問題行動に直面すると、親はつい「なんとかしなきゃ」と焦ってしまいます。
でも、焦りや怒りのままでは、問題はかえって長期化します。
だからこそ、まずは親自身が立ち止まり、冷静な視点を持ち、問題を修正していくことが大切です。
あなた自身も「回復の当事者」で、辛い気持ちを吐き出せたり、自身のありのままの感情を認めてあげる必要があります。
カウンセリングはその第一歩となる場です。
現状を変えたい方へ、構造的で実践的な関わり方を見つけるサポートをします。
まずは一度、状況を整理するためのご相談にお越しください。
Zoomでのオンラインカウンセリングも可能です。
遠方の方や多忙な方、家事の合間にも受けて頂きやすいようになっています。
ぜひ、お問い合わせください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓