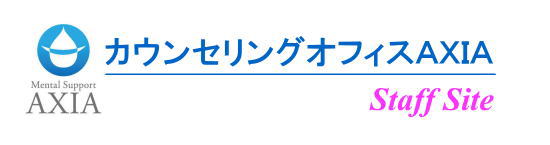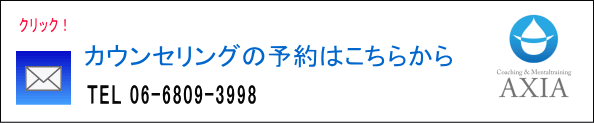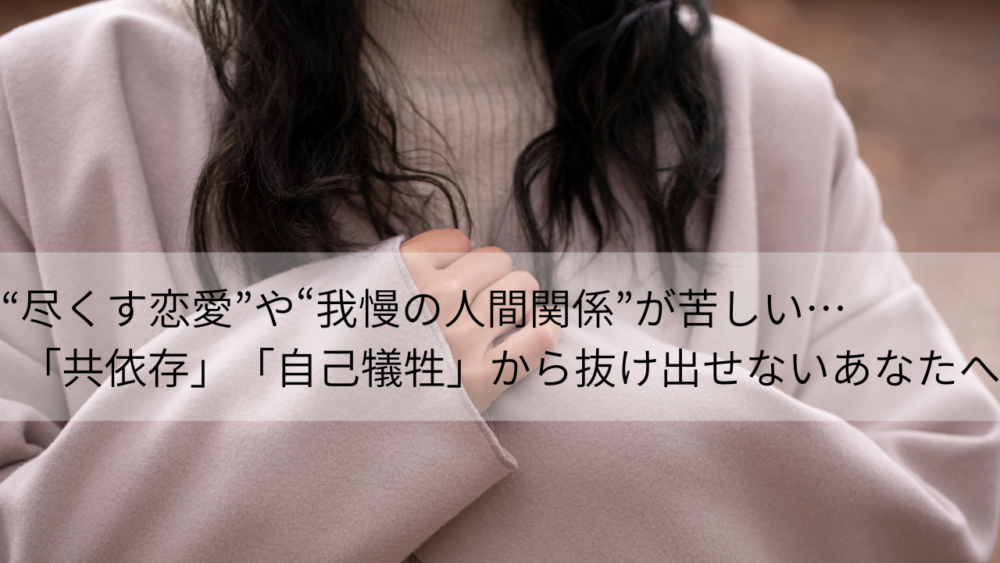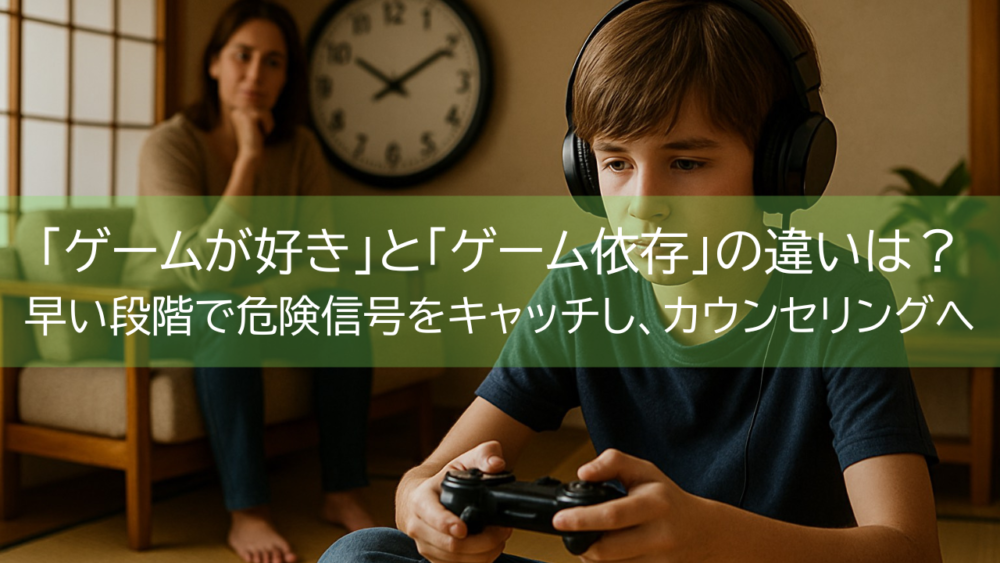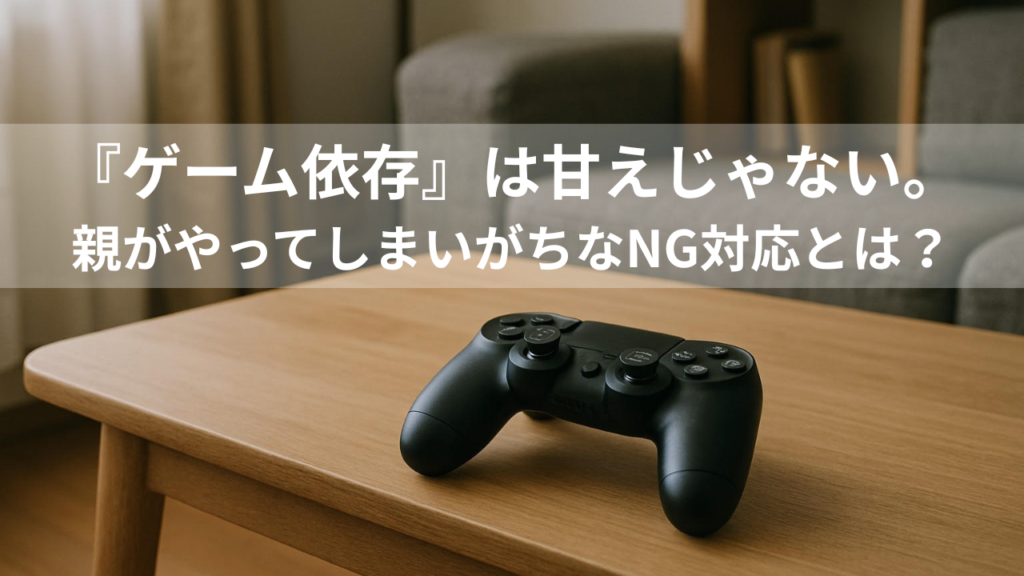
「何度言っても聞かない」
「いい加減にしてほしい」
「ただのわがままでしょ?」
そんなふうに思ってしまうくらい、子どもがゲームをやめられない――
それは、“甘え”や“やる気のなさ”ではなく、もしかしたら「依存状態」に近づいているサインかもしれません。
この記事では、親御さんがやってしまいがちなNG対応と、そこからの切り替え方をお伝えします。
◆「依存」は、意思の弱さではなく“コントロールの喪失”
まず知っておいてほしいのは、ゲーム依存は“ただの甘え”ではないということ。
やめないといけないのは分かってる。
でも、気づいたら手に取ってしまう。
一度始めると、やめ時がわからない。
これは意思の問題ではなく、「脳の仕組み」に近いところで起こるものなのです。
報酬系(ドーパミン)を強く刺激するゲームの構造に、子どもはハマりやすく、知らず知らずに依存状態に陥っていくのです。
そして、子どものうちから自制心が育たずにいると、大人になっても依存行動に陥りやすくなります。(ギャンブルやアルコールなど)
◆【NG対応①】「なんでできないの!?」と叱る
「昨日も言ったよね?」
「もう約束破るの何回目?」
「いい加減にしなさい!」
このような“正論で責める”対応、ついやってしまいがちですよね。
そのような気持ちになるのは当然のことと思います。
でも、これが続くと、子どもはこう思うようになります。
「どうせまた怒られるし、話したくない」
「部屋にこもって隠れてしよう」
つまり、親子の信頼関係が少しずつ削られてしまうんです。
叱ることが悪いわけではありません。
でも、「どうしてできないのか」を一緒に探る視点がないと、逆効果になってしまうこともあります。
◆【NG対応②】ゲーム機を隠す・壊す・取り上げる
強制的な方法では一時的には止まるでしょう。
しかし根本解決にならないどころか、こんな問題も起こりえます。
- 暴言や暴力など、攻撃的な反応
- スマホなど別の媒体への依存を移行する
- 親への信頼が完全に切れる
「ゲームを取り上げれば問題が終わる」という考えは、汚い部屋を片付けずに上から絨毯を敷くようなものです。
一見見た目は片付いたように見えても絨毯の下は散らかったままなんです。
本当に必要なのは、「なぜここまでゲームに頼ってしまうのか?」という“背景”への対処です。
◆【NG対応③】親が「放任」になる
叱るのも疲れた、取り上げても無意味――
そう感じて、次第に見て見ぬふりをしてしまう。
これもまた、実はよくあるパターンなんです。
そうすることで子どもの心の穴はどんどん大きくなり、ゲーム依存を加速させてしまいます。
放任は、「自由にさせてあげている」ようでいて、“孤立させてしまっている”こともあるんです。
では、どう接するのがいいのか?
ここで大事なのは、“敵にならないこと”です。
親が「やめさせよう」とすればするほど、子どもは防御反応を強めます。
代わりに、こんな対応を意識してみてください
- 「一緒に考える姿勢」を見せる
- 「どうしたらいいと思う?」と問いかけることで、子ども自身が“自分の状況に気づく”きっかけになります。
- 「できたこと」に目を向ける
概ね時間を守れたならそれを褒める
「どうしてそれができたと思う?」と振り返らせると、成功体験の積み重ねになります。
そして次は、ゲーム以外の楽しみを一緒に探すことが大切です。
何かを「奪う」よりも、「増やす」方が断然効果的なのです。
五感を使うものや体験に繋がるようなものが望ましいので親子で探し共有してみましょう。
◆「うちの子は依存なのかも」と思ったら
ゲーム依存には、「軽度→中度→重度」と段階があります。
「やめられない」
「生活に支障がある」
「他のことに無関心」…
そう感じたら、すでに“対応が必要な段階”かもしれません。
でも、焦る必要はありません。
大切なのは、子どもの無意識のSOSに気づくことです。
そして、一人で抱え込まずに、「誰かに相談すること」です。
カウンセリングでは、“親のせい”にすることはありません。
親御さんの中には、「私の育て方が悪かったのかも」と自分を責めてしまう方も多くいらっしゃいます。
誰かを“悪者”にするのではなく、どう関係を整えていくかを一緒に考えます。
- 子どもにどう声をかけたらいいかわからない
- 夫(妻)と考えが合わなくてつらい
- 何を信じていいかわからない
そんな迷いやしんどさも、遠慮なく話していただけます。
◆最後に:親ができることは、たくさんあります
ゲーム依存は、一人で抱えるには大きな問題です。
でも、正しい知識とサポートがあれば、少しずつでも、必ず変化は起こせます。
「そんなことで変わるとは思えない」
そう思われる方もいるかもしれません。
しかし、”そんなこと”でも行動に移さないのであれば変わることはあり得ません。
「もしかしてうちの子…?」と思ったときが、実は“変わるための最初のタイミング”かもしれません。
気づいた今、はじめの一歩としてまずはご相談ください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓