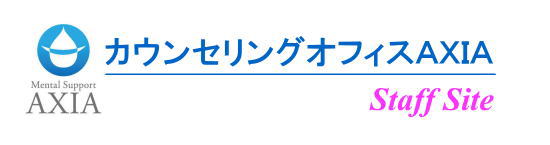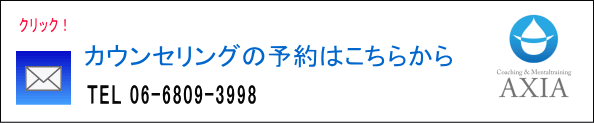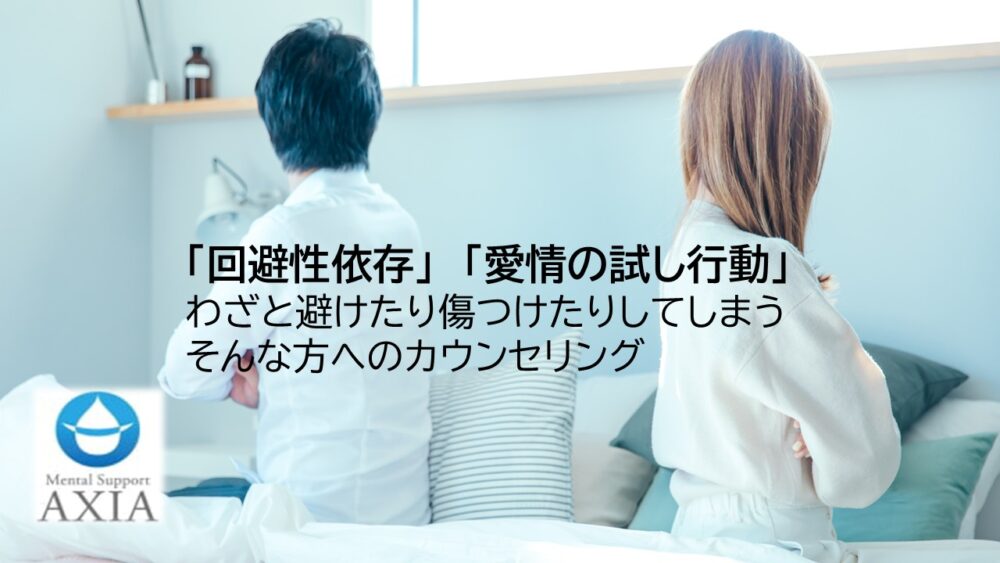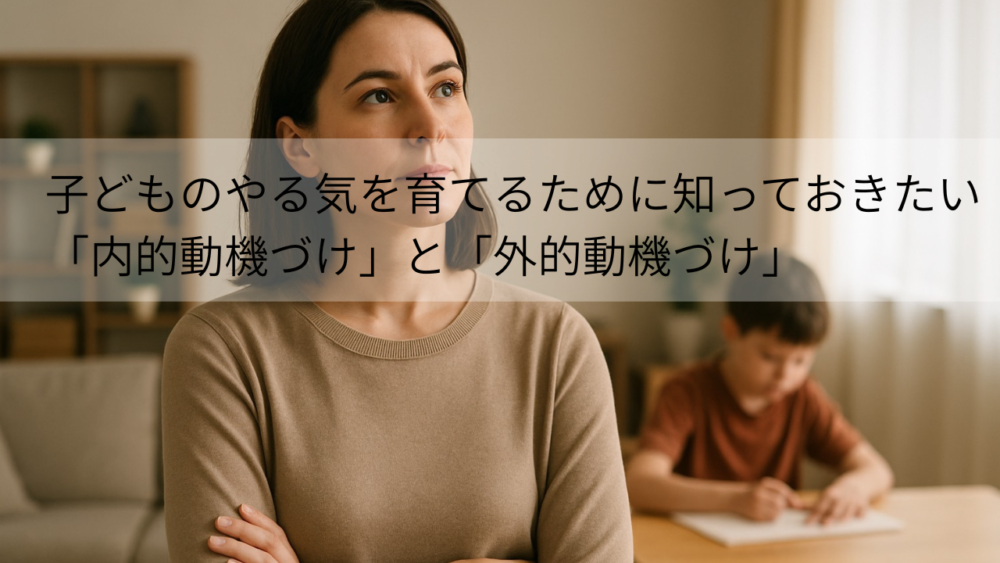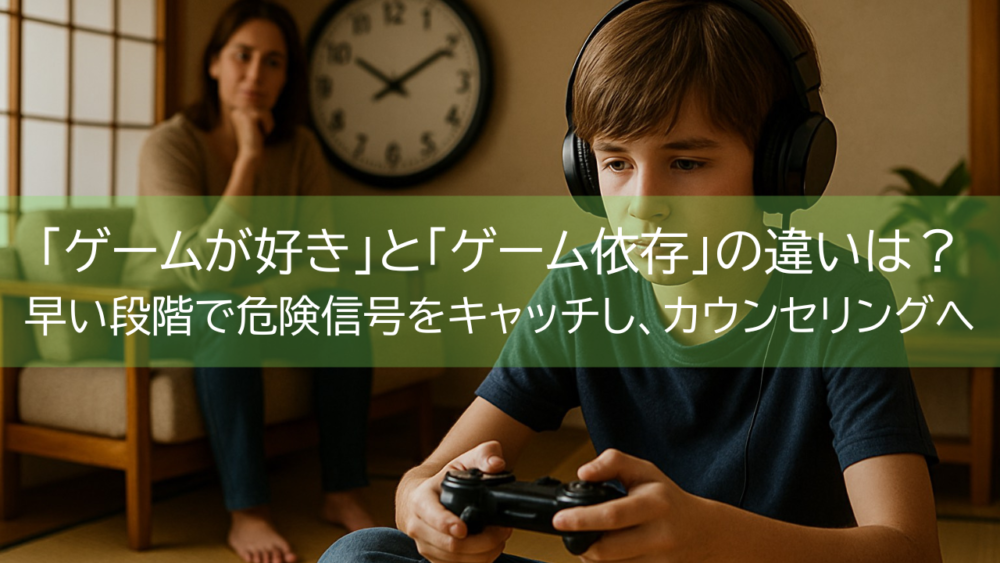◆他の子と比べてしまう親心
子育てをしていると、「うちの子はうちの子のままでいい」と思いながらも、つい他の子と比べてしまうことがありますよね。
保育園や学校での様子を見たときに「あの子はできてるのに、うちの子は…」と感じてしまう…。
ママ友の会話の中でつい、「うちの子もこうなってほしい」と期待してしまったり…。
モヤモヤしたまま帰宅してつい子どもに厳しく当たってしまうこともありませんか?
そしてそんな自分に罪悪感や自己嫌悪に襲われることもあるでしょう。
◆周りの子どもと比べてしまう、という罪悪感
「他の子はちゃんと話を聞いてるのに」
「なんでうちの子はできないんだろう」
そんな風に思ってしまって、「比べたくないのに比べてる…」と自己嫌悪に陥る。
でも、比べるのは当然のことなんです。
自分の子が社会の中でうまくやっていけるか、不安になるのは親として自然な感情。
問題は「比べたこと」じゃなくて、そのあとにどう受け止めていくかなのです。
「この子にはこの子のペースがある」と言えるようになればいいのに…と思うけどそれが難しい。
それは、親自身に劣等感や焦りがあるパターンが考えられます。
まず親自身が、“自分はこのままでいい”と感じられていることが前提なんです。
◆親の心の課題が背景にある
こうした感情の背景には、親自身の焦りや心の課題が隠れています。
例えば:
- 自分が経験できなかったことを子どもにさせてあげたい
- 自分が達成できなかった夢や理想を子どもに託している
- 他人から認められたいという気持ちが強く、子どもを自分の「成功の証」にしたい
知らず知らずのうちにこうした思いは、プレッシャーとして子どもに伝わり、親子関係に影響を与えます。
「子どものために」が本当にそれだけなのかを一旦立ち止まって考えることも大切です。
さらに、ママ友や周囲との比較も、親の心の焦りを映す鏡です。
「うちの子は遅れていないか」「他の子よりできていないのでは」という不安は、親の承認欲求や自己評価の揺らぎから生まれることがあります。
承認欲求や自己評価を揺らがされる付き合いを制限することも一つの方法です。
もしくは、自身の承認欲求や自己評価の揺らぎに気づき改善していくこともできます。
◆自分の焦りに気づくことの大切さ
まずは、自分自身の内面に意識を向けることです。
自問してみましょう:
「なぜ他の子と比べてしまうのか」
「この期待は子どものためなのか、それとも自分のためなのか」
自分の感情の根っこに気づくだけでも、関わり方は少しずつ変わってきます。
例えば、子どもが苦手なことを見つけたとき、「ここは一緒に少しずつ取り組もう」と思えるか、「できないと(自分が)嫌」「もどかしくてイライラしてしまうか」では、接し方が大きく変わります。
◆カウンセリングの活用
自分だけで気づくのが難しい場合、カウンセリングを活用するのも有効です。
-
- 話すことで、自分の感情を整理できる
- なぜその焦りや期待が生まれるのかを客観的に見つめられる
- 「自分は完璧でなくてもよい」「子どもの成長の形はひとつではない」と理解できる
誰かに話すことで、自分の焦りや期待を客観視でき、少しずつ親としての安心感を取り戻せます。
カウンセリングは「解決策を与える場所」ではなく、親が自分の心を理解する安全な場です。
自分の気持ちに向き合うことで、子どもとの関係も自然と落ち着いてきます。
◆ 最後に:自分を責めないこと
親として完璧である必要はありません。
大切なのは、自分の心の動きを理解し、意識的に子どもと関わることです。
「ついイライラしてしまった」「比べてしまった」と感じた瞬間も、振り返りの材料になります。
焦りやプレッシャーに気づくことで、子どもとの関係をより良くできるのです。
もし、自分の感情に振り回されることが多いと感じたら、カウンセリングを試してみるのもひとつの方法です。
話すことで自分の課題を理解し、子どもにとっても自分にとっても優しい関わり方を見つけることができます。
親の焦りは誰にでもあります。
でも、それに気づき、少しずつ整理することで、子どもにとっても、自分自身にとっても、より優しい日々を作ることができます。
焦りや不安を「悪いこと」と責めるのではなく、理解して受け止めることから始めてみませんか。
「他の子と比べてしまう」「もっとこうなってほしいのに」という気持ちに苦しんでいる親御さんは一度ご相談ください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓