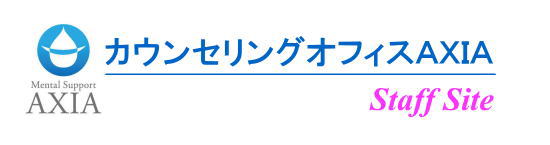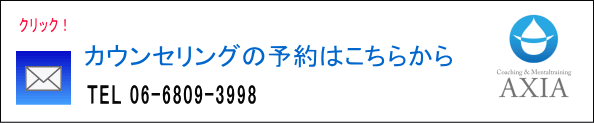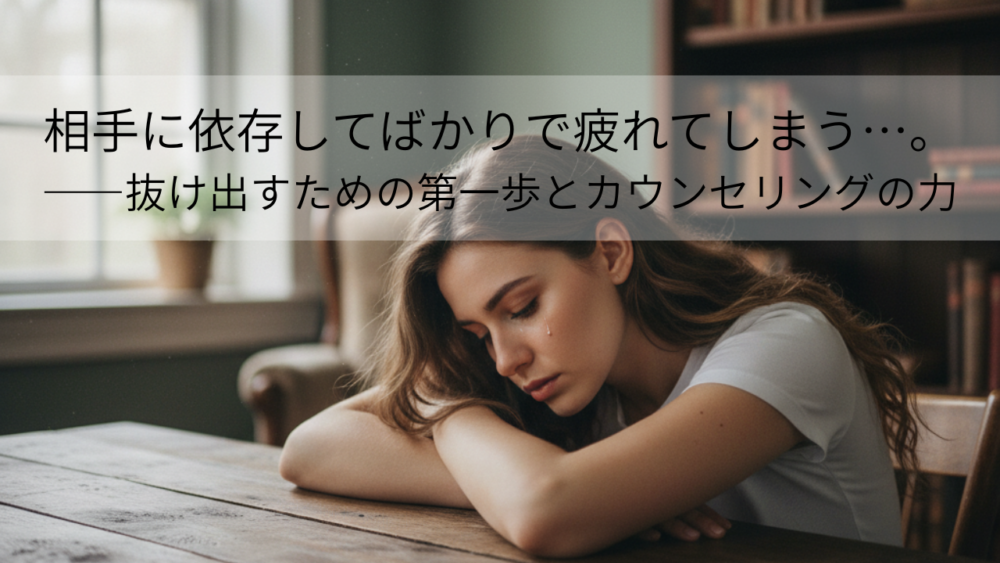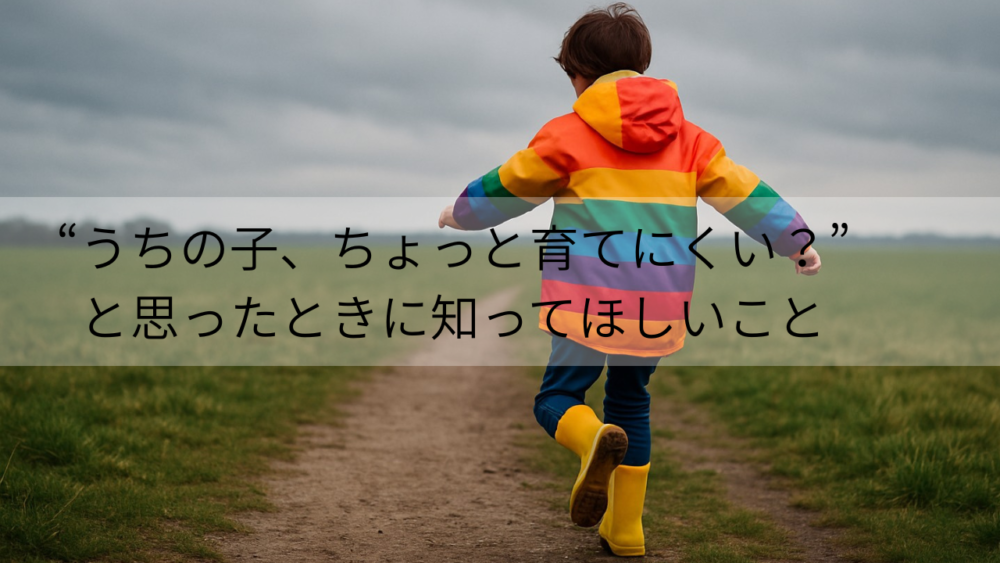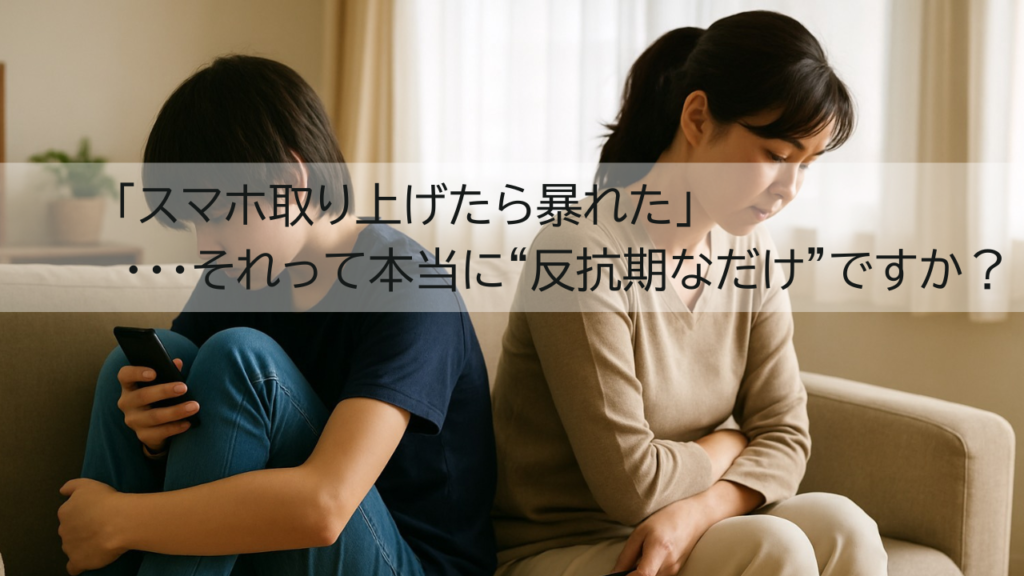
最近、こんなことはありませんか?
ゲームやスマホを取り上げた瞬間、怒鳴る・暴れる・物に当たる…。
ルールを決めても、一切守ろうとしない目を合わせてくれない、部屋から出てこない。
「思春期ってこういうもんかな…」「うちの子、反抗期に入ったのかな…」
そう思って見守ろうとしているあなたに、少しだけ立ち止まって考えてほしいことがあります。
それ、“反抗期”ではなく“依存のサイン”かもしれません。
◆本来の“反抗期”とは?
反抗期とは、自我の確立や、親からの心理的自立の一歩として起こる自然なプロセスです。
自分の意見を主張したがるけれど、根底には親への信頼や甘えが残っているような時期でもあります。
ところが、ゲーム依存やスマホ依存が絡む場合は、その反応の質がまったく違ってくるのです。
依存のサインは“理性を飛ばしたような反応”で、
- 机や壁を殴る
- 物を投げる大声で叫ぶ
- 暴言を吐く
- 自分を傷つけるような行動をとる
こうした反応は、単なる感情表現ではなく、「奪われた」ことへの過剰な防衛反応です。
これは、“依存対象”がなくなったことで起こる「離脱症状」に近いとも言えます。
親の立場からすると、「こんなに怒るなんておかしい」「どうしてここまで…」と戸惑って当然です。
◆「暴れる=ダメな子」ではない
ここで大切なのは、子どもを責めすぎないこと。
暴れてしまうのは、「やめたくてもやめられない」苦しさの裏返しなのです。
本人も、心のどこかで「自分でもコントロールできていない」と感じている場合も多いです。
でもそれを言葉にできない無意識の困惑があるからこそ、暴力や無言という形でしか表現できないのです。
◆取り上げれば解決?実は逆効果なことも
まず最初に親がやりがちなのが、「問題行動=物理的に遮断」という対応です。
- スマホ/ゲーム機を隠す
- Wi-Fiを切る
- スマホを没収する
もちろん行動に制限をかけることは大事なことでもあり、即効性があるように思われます。
短期的には“止まる”かもしれませんが、根本解決にはつながりません。
むしろ、こんなリスクもあります。
- 親への不信感が強まる
- 隠れてプレイするようになる,嘘をつくようになる
- 他の依存(動画・SNSなど)に移行する
では、どうすればいい?
◆スマホ・ゲームとの「付き合い方を一緒に考える」
スマホやゲームが悪いものだと決め、禁止にする選択をする方も多いと思われます。
しかし、一生親が目を光らせてスマホやゲームを制限することはかなり困難です。
親が仕事をしている間や、大学生活で実家を離れてから…などいつでも依存するタイミングはあるのです。
むしろ禁止にされていた分、それが解放される時は一気にのめり込むリスクもあります。
今後一生スマホやゲームに触れない生活は、今の現代では不可能です。
「やめなさい」ではなく、「どうしたらやめられそう?」と、正しい距離感を子どもと一緒に考えるスタンスが大切です。
◎「話せる環境」を作る
まず大切なのは環境作りです。
親に見張られていると感じると、子どもは心を閉ざし、隠し事が増えてしまいます。
しかし、「じゃあ安心して話してね!」と言ってすぐに話しだせるものでもありません。
子ども自身も何を話していいのか分からなかったり、話しだすのに勇気が必要だったり…
話せる環境はすぐに出来上がるものではありません。
何気ない会話や一緒に過ごす時間を増やすことで、徐々に本音を話しやすくなる関係性の構築が必要です。
◎「ゲームの背景」に目を向ける
ゲームは表面上は趣味や娯楽のもので、「甘えてる」「怠けてる」と捉えてしまうのも無理はありません。
しかし、その背景には寂しさやストレスや自信のなさ、生活の中の虚無感などさまざまです。
ゲームに打ち込まなければいけない心の不安定さや満たされない感情が隠れていることがよくあるのです。
◎すぐ解決しようとしない、原因追及しない
すぐに禁止したり、ペナルティを課したりしない。
前述した通り、親子の心の溝を生んでしまいます。
「しつけがなってない」と自己嫌悪になったり、「私の育て方が悪かったんだ」と責任を感じてしまうこともあります。
そんなふうに感じるのは自然なことですが、ゲーム依存は親が悪いわけでも、子どもがだらしないわけでもありません。
これは、“対応の仕方”を少しだけ見直すことで、大きく変わることができる問題なんです。
◆一人で悩まず、相談してみませんか?
暴れる子どもにどう接していいかわからない…。
「私の言うことなんて、もう届かない気がする」そんなふうに感じたら、一度お話しにきてください。
カウンセリングでは、
- 親子の関係を再構築するための関わり方
- 依存の本質と向き合うアプローチ
- 日常で使える具体的な声かけや習慣づくり
などを、親御さんの状況に合わせて提案しています。
子どもが暴れるとき、それは「聞いてほしい」「わかってほしい」そんな必死のSOSのメッセージかもしれません。
「反抗期だから仕方ない」ではなく、「今、何を伝えようとしているのか」を一緒に考えていきませんか?
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓