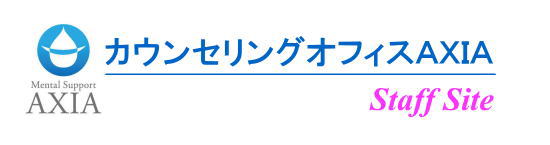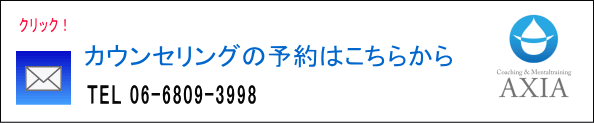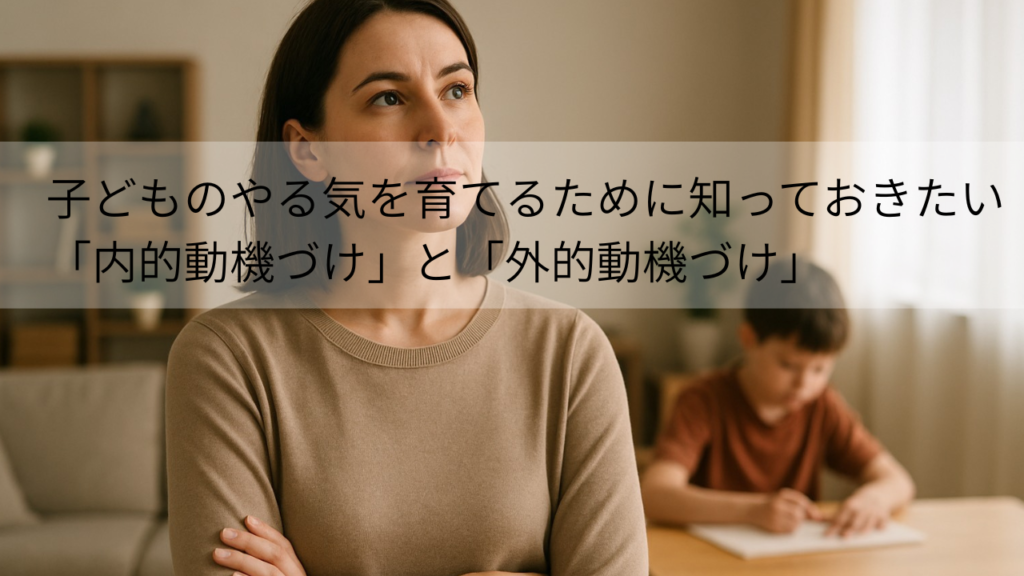
子どもが学校に行きたがらなかったり、なかなかやる気を見せなかったりする。
そんな時、「できなかったら叱る」「行ったらご褒美をあげる」といった対応になりがち・・・。
その報酬や罰は、子どもの「やる気」にどんな影響を与えているのでしょうか?
◆「内的動機づけ」と「外的動機付け」
◎内的動機付けとは?
内的動機づけとは、子どもが自分の心の中から自然にわき上がる「やりたい」「面白い」「達成感を味わいたい」といった気持ちです。
たとえば、
- 好きな友だちと会えるから学校に行く
- 得意なことを伸ばしたいと思う
- 自分で目標を決めて達成したい
こうした気持ちは、自分の意志で行動する力になり、長続きしやすいのが特徴です。
◎外的動機づけとは?
外的動機づけは、周りからの報酬や罰によって行動を促されることです。
たとえば、
- 「学校に行ったらお小遣いをあげる」
- 「宿題をしなかったらゲーム禁止」
- 「怒られるのが嫌だから勉強する」
こうした外からの刺激で動くことを指します。
すぐ行動には繋がりますが、長続きせず、”抜け道”を探したり”脇道”に逸れてしまう傾向があります。
◆報酬や罰がもたらす影響
報酬や罰は短期的には効果的に見えることもありますが、長い目で見ると注意が必要です。
1. 報酬が「やる気」を奪うこともある?
外からの報酬ばかりに頼ると、子どもは「報酬のために動く」ようになります。
そのため本来自分が感じる楽しさや達成感を味わいにくくなります。
私たち大人も、報酬のために仕事をしていますが、就職した当時と今では仕事へのやる気はどうでしょうか。
「内的動機づけ」が意識されていれば、仕事をこなすことで自己成長や達成感を感じることができます。
ただ、最初は好きで選んだ仕事でも、仕事である限り報酬はつきもので、報酬に意識を向けるのは当然です。
楽して稼ぎたい気持ちや、サボりがちになったり、出勤が嫌になった経験はありませんか?
そして、報酬は常に上がり続けないとやる気を維持することはできないものです。
「最初はお菓子や漫画だったのに、今では数万円のゲーム機…ついに現金にも…」なんてことになります。
2. 罰は恐怖や反発を生みやすい
罰を使うと一時的に行動を手っ取り早く変えることができます。
しかし、子どもはストレスや恐怖を感じたり、親に対して反発したりすることも…。
親が見ている時だけやっているフリをしたり、やったと嘘をついたり、あるいは宿題の答えを写するなど本来の意味を無視した行動に繋がります。
親からすれば表面的にはやっているため楽な躾かもしれませんが、根本的な解決にはつながりにくいです。
◆どうすれば内的動機づけを育てられる?
- 子どもの気持ちに寄り添うこと
「なぜ行きたくないのか」「何が不安なのか」を一緒に考え、子ども自身が自分の気持ちに気づけるように支えてあげる。
”子どもの語彙力は親の語彙力”と言われるくらい言葉での関わりが大きく影響します。
- 小さな成功体験を積ませること
できたことをしっかり認め、達成感を味わわせると、「またやってみよう」という気持ちが育ちます。
この気持ちが育つと、都度「やりなさい」と言い続けなくとも子どもが自分にとって必要だと感じたことを選択して取り組めるようになります。
- 選択肢や自由を与えること
自分で決められる範囲を広げることで、自己決定感が高まりやる気が増します。
自己肯定感を育むことはもはや単純に能力や学力だけの問題ではなくなります。
コミュニケーションや人生そのものへの幸福度とも大きく関連しています。
◆カウンセリングでサポートを受ける意味
カウンセリングは、
- 子どもの気持ちを専門家に話すことで整理できる
- 親御さん自身の悩みや不安を軽くできる
- 子どもとどう向き合えばいいか、具体的な方法を一緒に考えられる
- 家族全体のコミュニケーションを良くしていける
といったメリットがあります。
「どんな声かけが効果的か分からない」「親子でどう接したらいいか悩んでいる」
そんな時にこそ、カウンセリングは大きな助けになります。
決して一人で頑張る必要はありません。
◆まとめ
- 報酬や罰に頼りすぎると、子どもの「本当のやる気」が育ちにくいことがある
- 子どもの気持ちに寄り添い、小さな成功や選択肢を増やすことが大切
- 親御さんも自分の心のケアや感情の整理を大切に
- カウンセリングは親子の関係を支え、よりよい方向に導く強力なサポートになる
子どもの心が少しでも軽くなり、笑顔で毎日を過ごせるように。
困ったときはまずは相談することで「話せる場所」を作ることが大切です。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓