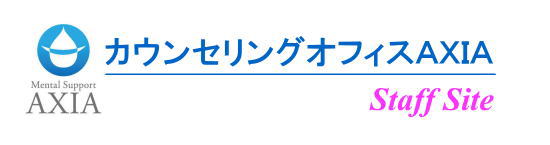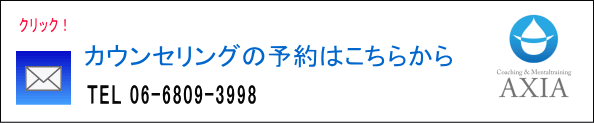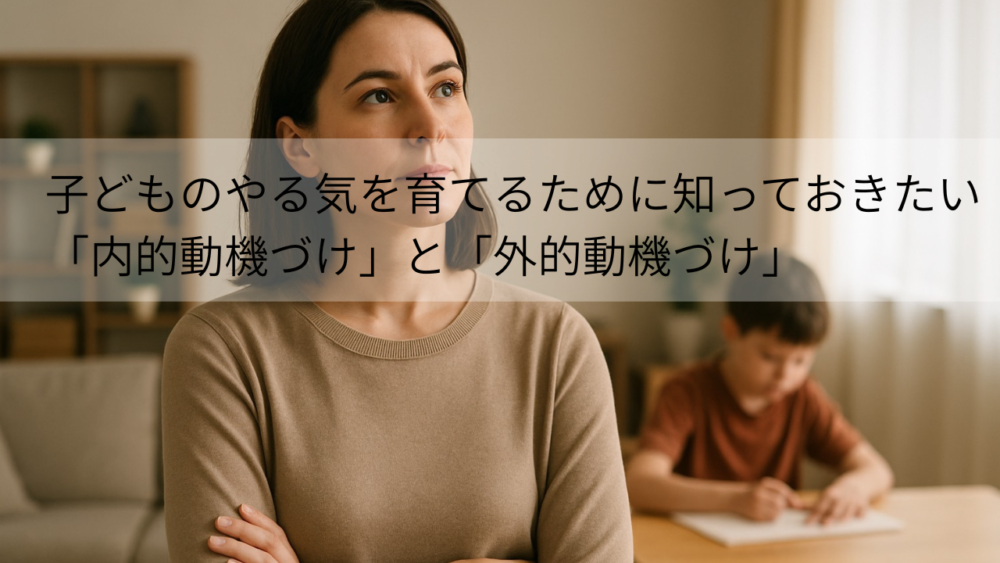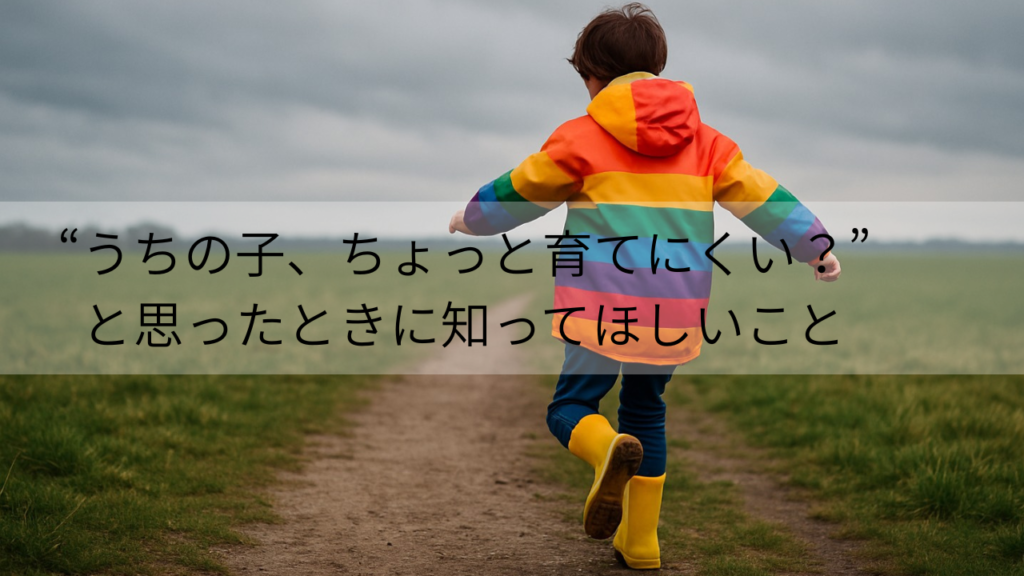
「他の子と比べるのはよくない」とわかっていても、やっぱり比べてしまう。
幼稚園や小学校での様子を聞くたびに、「うちの子ってちょっと違うのかも」と不安になる。
そんなモヤモヤを抱えているお母さんは、実は少なくありません。
でも、その「育てにくさ」に言葉を与えることって、意外と難しいんですよね。
ただ「落ち着きがない」「こだわりが強い」「癇癪がひどい」と言ってしまえば、それはただの困った子。
でも、“何か理由があるのかもしれない”という気づきこそが、親としての第一歩なんです。
◆「診断があるかないか」より、今の関わり方が大切
最近は「発達障害」という言葉もずいぶん浸透してきましたね。
でも実際には、診断がつく子ばかりではありません。
「グレーゾーン」と言われたり、「傾向がある」とだけ言われて終わってしまうことも。
そんなとき、親としては判断に迷いますよね。
「この子には療育が必要? でも普通級でやっていけるかも?」
「過保護すぎるのかな? でも放っておくのは不安…」
実は、“診断を待ってから動く”必要はありません。
診断よりももっと大切なのは、今、子どもとどう関わるか。
目の前のことで困っているなら、その困りごとに対してできる工夫やサポートを探していけばいいんです。
◆「親の育て方が悪いのでは?」と思ってしまう背景
カウンセリングで耳にすることが多いのは、「私のせいなんでしょうか…」という言葉です。
毎日怒ってばかりの自分、優しくできない自分に嫌気がさす…
「この子を困らせているのは自分なんじゃないか」と思い込んでしまう…
でも、これは自己否定や共依存のサイクルに入りやすいお母さんほど、陥りやすい考え方。
本当は、「この子に合った関わり方を一緒に探していけばいい」だけのことなのに、なぜか“自分のせい”という結論に急いでしまうんです。
原因探しや結論を急ぐことは、”今”を見つめる目を曇らせてしまいます。
大切なのは今目の前にいる子どものことをどれだけ知っていけるか、向き合っていけるかなのです。
◆周囲との温度差が、悩みをこじらせる
「先生は“そんなに気にしなくても大丈夫”って言うけど、家では毎日大変」
「夫は“そのうち落ち着く”と言って、協力してくれない」
「親に相談したら“神経質すぎる”って言われた」
…この“温度差”は、ママの不安やストレスを何倍にも膨らませます。
誰かが「わかるよ」と言ってくれたら、それだけで整理できることもあるのに、「気にしすぎ」と言われると言葉を飲み込んでしまうんですよね。
そのうち、「何を言ってもわかってもらえない」という孤立感が強くなり、一人で考え続けて疲れ果ててしまいます。
◆特性に合った“ちょっとした工夫”で変わることがある
ゆっくりペースの子に対して周囲の子たちと同じスピードを求めると、一時的にはできても”ガソリン切れ”状態になります。
そうすると子ども自身が挫折を味わってしまい、立ち上がるのにも時間がかかってしまいます。
長い学校生活、長い人生において、一時的になんとか凌ぐのではなく長期的に無理のない習慣づけをするな目線が必要です。
例えば、
急な予定変更が苦手な子には「視覚的なスケジュール」を取り入れる。
感覚が過敏な子には、「大きな声ではなく、静かに近づいて話す」だけでも変わる。
特性に合った関わり方って、決して大げさな療育や専門知識が必要なものばかりじゃないんです。
ただ、その子に合った“声のかけ方”や“環境の作り方”を一緒に考える人が、そばにいるかどうかで全然違ってきます。
◆「何が正解か」はなくても、「選べる視点」はある
子どもにとって何が最善か、正解なんてどこにも書いてありません。
でも、「考えられる選択肢」が少しでも増えれば、親の焦りや不安は減っていきます。
「この子はこういうタイプかもしれない」
「だったらこう関わってみよう」
その繰り返しが、少しずつ親子の関係を柔らかくしていくんです。
◆カウンセリングでできること
カウンセリングは、「答え」を渡す場所ではありません。
でも、「どうしたらいいかわからない」という気持ちを抱えて動けなくなっている状況を整理し直す場所として、とても有効です。
- 子どもの特性をどう理解していけばいいか
- 自分の考えや感情をどう整えればいいか
- 夫や学校とどう連携すればいいか
そういったことを、自分ひとりの責任にせずに、話し考え一緒に整理しながら探していく場です。
子どもは意外と親の様子や表情に敏感です。
お子さんと向き合うため、親自身がメンタルを整えていく必要があります。
◆さいごに
「ちょっと育てにくいかも」と思ったとき、
「私が間違ってるのかな」と感じるとき、
それは「もっと良くしたい」と思っている証拠です。
あなたの考えや気持ちを、一緒に言語化して整理する時間を取ってみませんか?
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓