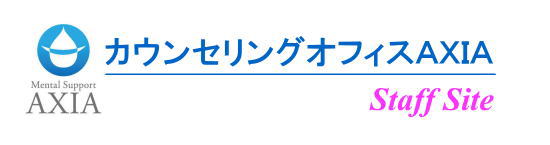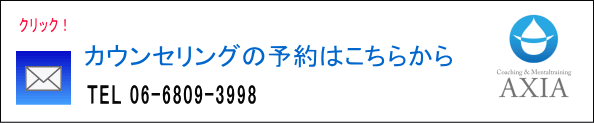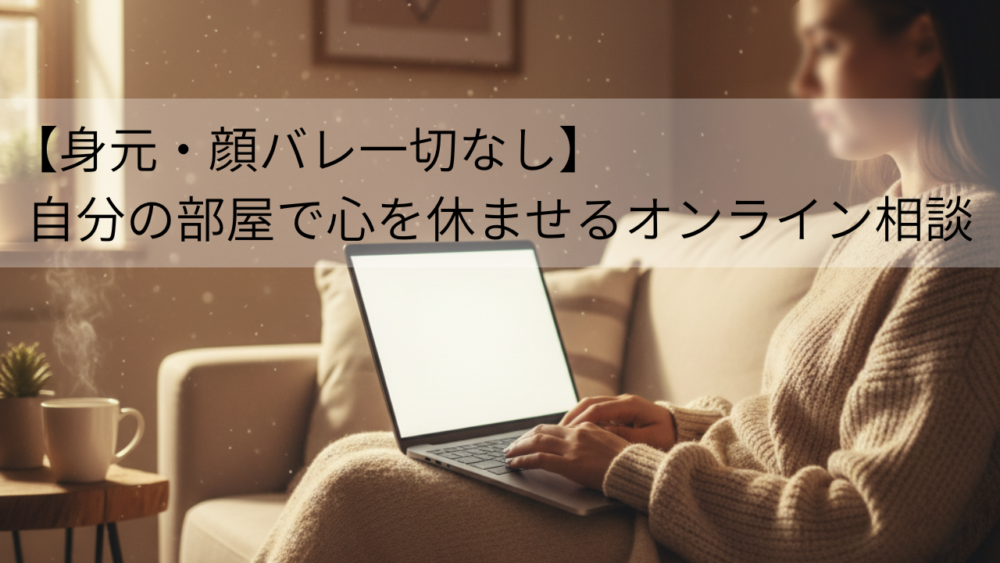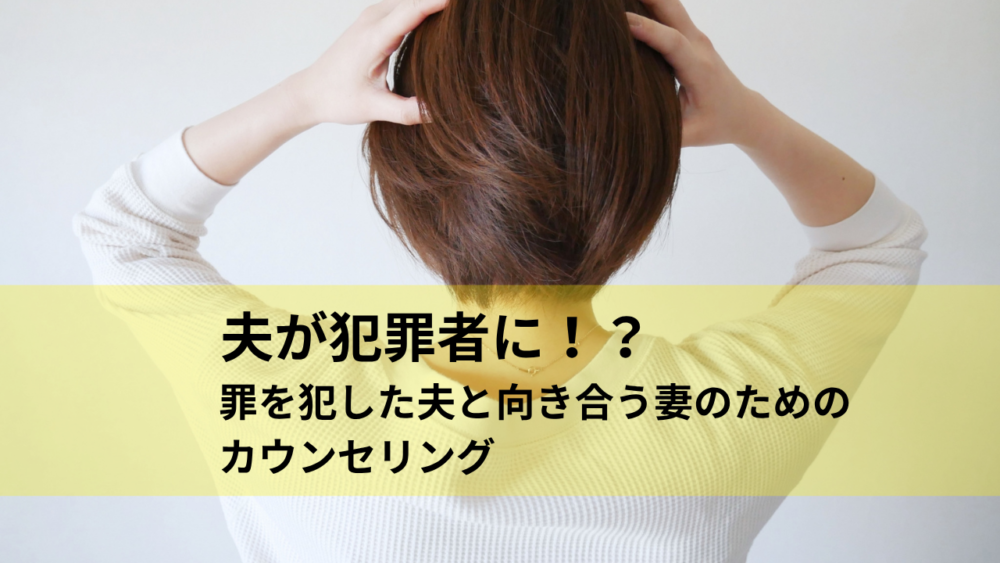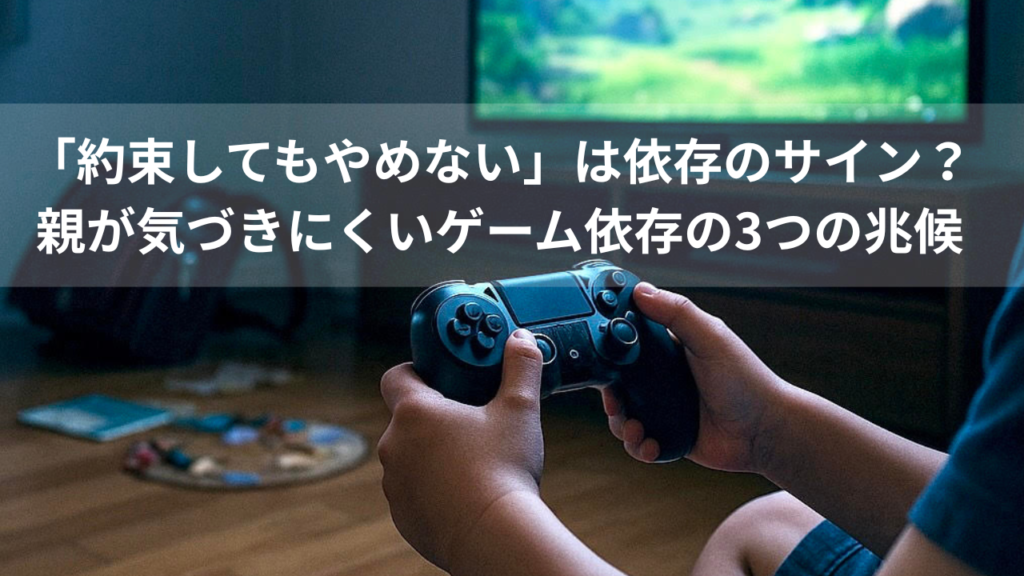
「今日は1時間だけって約束したよね?」
「明日はテストなんだから、ゲームは控えようって言ったでしょ?」
そう言っても、子どもがやめない――そんな経験はありませんか?
「まぁ、約束を守れないことくらいあるよね」と流してしまいがちですが、実はそれ、ゲーム依存の“初期サイン”かもしれません。
この記事では、ゲーム依存における“親が気づきにくい兆候”を3つ紹介しながら、どう向き合えばいいのかを考えていきます。
◆兆候①:口では「やめる」と言うけど、行動が伴わない
ゲームをやりすぎて叱られた時、
「気をつける」
「今日はもうやめる」
と言う子は多いですよね。
でも、結局すぐにまたゲームを始めてしまう。
これは、「嘘をついている」とは限りません。
本人も“やめたい”という気持ちがあるのに、意思だけではコントロールできない状態――
依存症の入り口でよく見られる姿です。
ここで大事なのは、「意志が弱い」と決めつけないことです。
親としては、「前も同じこと言ってたでしょ!」と責めたくなる気持ちも大いにあるかと思います。
しかし、そこはぐっとこらえて、“子ども自身も困っている”という視点を持つことが大切です。
これはゲームを”許容する”や”寛容的な親になる”という意味ではありません。
約束しても叱ってもやめられないなら、違った形でのアプローチが必要なのです。
◆兆候②:ゲームのためにウソをつく・隠すようになる
たとえば…
- 「宿題終わった」と言ってゲームを始める(実は終わってない)
- 親の目を盗んで夜中にゲームをしている
- スマホのパスコードを変える、見えないように隠す
こうした行動は、叱ったりスマホ・ゲームを取り上げるなどをした場合によくみられる兆候です。
でも、ここで注目してほしいのは、「なぜそこまでしてでもやりたいのか?」という部分。
それは、単に「楽しいから」「ゲームが好き」だけではありません。
“やらないと不安”になったり、“他に楽しみがない”といったぽっかりと穴が開いた部分を埋めるための行動なのです。
◆兆候③:ゲーム以外のことに関心がなくなっていく
「以前はよく外で遊んでいたのに、今はゲームばかり…」
「家族と出かけても、スマホが気になっているよう」
「何をしていても「早くゲームやりたい」と言う」
そんなふうに、“生活の中心がゲームになる”というのは、依存傾向の典型です。
特に思春期の子どもに多く見られますが、親からすると「ただ飽きっぽいだけ?」「子どもだし夢中になってるだけでしょ?」と軽く見てしまいがちです。
しかし、「ゲーム以外で喜んだり、笑ったりする姿が減った」と感じるようなら、少し注意が必要です。
それは、“心のエネルギーが枯れている”サインかもしれません。
◆頑張ってもコントロールできないのが「依存」
親としては、ルールを決めたり、叱ったり、工夫しているつもりでも、なかなか変化が見えないと焦りますよね。
しかし、ゲーム依存の特徴は、「本人もやめたくてもやめられない」という“コントロールの難しさ”にあります。
これは、“甘え”や“性格の問題”ではありません。
むしろ、気づかないまま放っておくと、学業や人間関係、自尊心にも影響を及ぼすケースがあります。
大人になって依存傾向があるままだと場合によってはギャンブル依存やアルコール依存など形を変えて出現してしまいます。
”依存に対するコントロールする力”を子どものうちから培っていくことも大切です。
◆「うちの子もそうかも…」と思ったらまずは相談を
「子どもなんてみんなそんなもん」
「ただの反抗期かと思っていた」
「最初はそんな深刻ではなかった」
と、実際に相談に来られた親御さんたちはおっしゃいます。
だからこそ、「気づいたときに、親としてできることを探したい」そう思ったその時が、第一歩を踏み出す時になります。
今この記事をここまで読んでくださった方は何か気になることがあるのではないでしょうか。
◆一人で抱えず、専門家に頼ってみませんか?
ゲーム依存は、放っておいて自然に改善するケースはあまり多くありません。
子どもが“自分の状態に気づける”ように促すには、時間とコツがいります。
周囲や夫に相談しようにも、
「みんなそんなもんでしょ」
「躾の仕方が悪いんだよ」
など、あまり理解が得られないという声も多く耳にします。
当カウンセリングルームではゲーム依存に悩む親御さんを対象にしたカウンセリングを行っています。
怒っても、泣いても、変わらない――。
そんなときこそ、誰かの視点が入ることで、大きく変わることがあります。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓