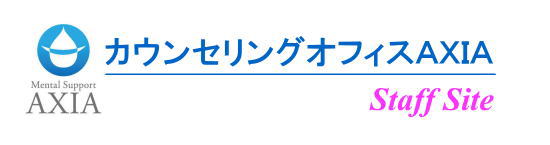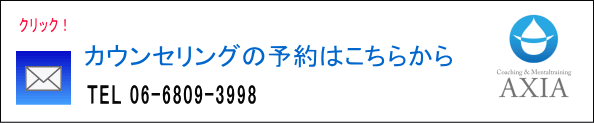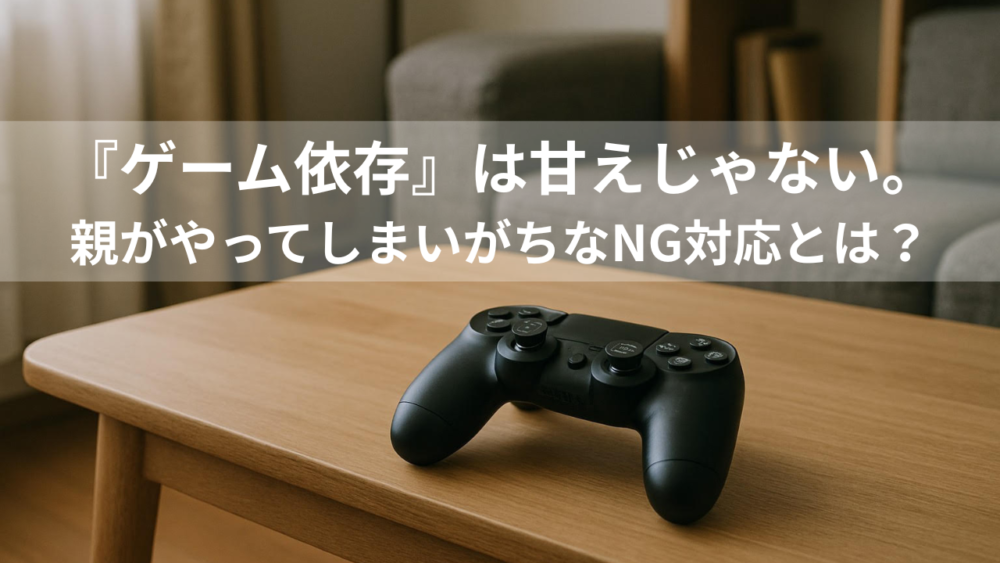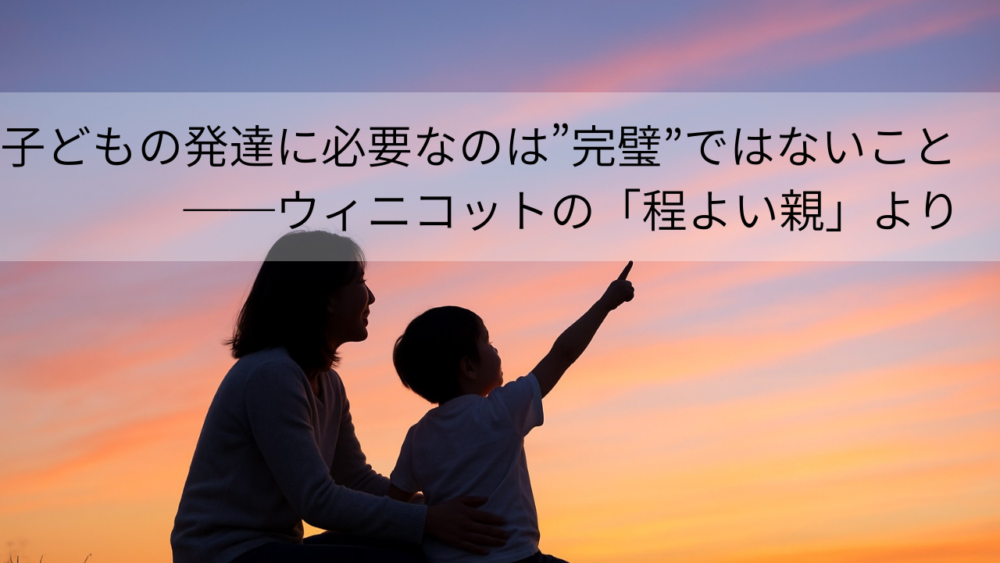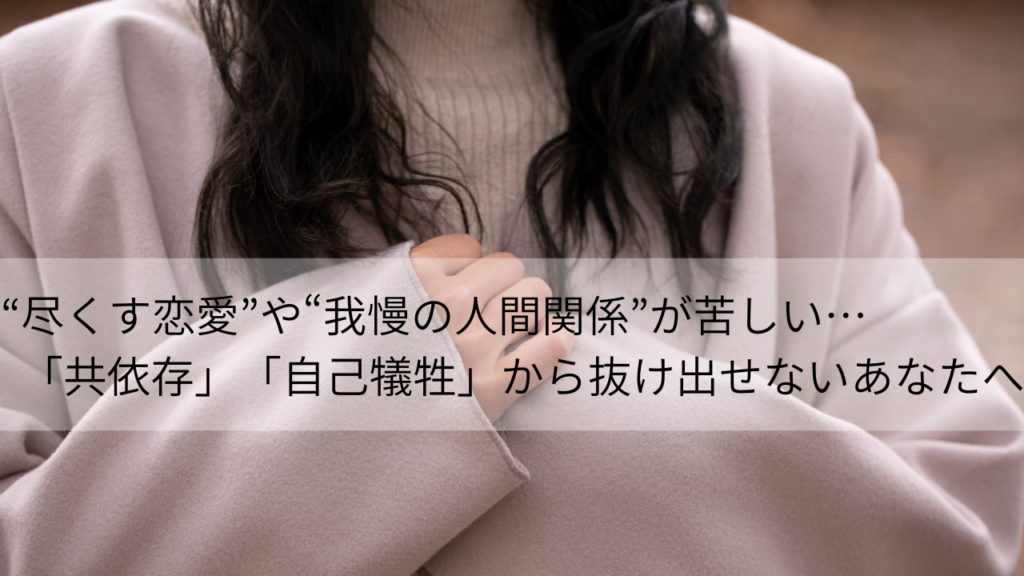
◆自己犠牲・共依存とは「人のため」に見せかけた自分の喪失
「自分が我慢すればうまくいくならそれでいい」
「世話することで感謝され、自分の価値が見出いだされる」
「自分がどうしたいかよりも相手の要望を聞き入れる」
こうした考えに縛られている状態を、心理学では自己犠牲傾向や共依存と呼びます。
どちらも根底には、“見捨てられる不安”や“無価値感”が潜んでおり、無意識のうちに「人に尽くすことでしか自分の存在価値を感じられない」状態になっているのです。
◆典型的な共依存のパターン
共依存は、親密な関係の中で特に現れやすく、以下のようなパターンが繰り返されます。
- 相手に依存されると安心する
- 問題のある相手(浮気・DV・依存症など)から離れられない
- 相手を支えることが“使命”になっている
- 相手に尽くしても感謝されず、むしろ雑に扱われる
- 自分の感情やニーズがわからなくなっている
一方で、「助けたいのに報われない」「傷ついているのに関係をやめられない」といった強いジレンマを抱え続けます。
◆なぜこの関係から抜け出せないのか?
共依存や自己犠牲的な関係性は、「苦しい」と頭でわかっていても、なぜか手放せない依存性の高い構造を持っています。
その理由は、主に以下の3つの心理的背景によって支えられています:
① 幼少期の「条件つきの愛」体験
・「いい子にしていないと受け入れてもらえなかった」
・「親が不安定で、自分が支える側だった」
その結果、大人になっても”相手に尽くして初めて価値がある”と思い込んでしまうのです。
このような家庭環境で育つと、“自分より他人”を優先することが愛される条件になってしまいます。
② 感情の抑圧と無感覚化
自分の気持ちや欲求を無視し続けることで、次第に「何が好きで何が嫌なのか」「何を望んでいるのか」さえわからなくなる状態に陥ります。
筋肉を使わないと衰えていくのと同じように、考えることをしないと感情を感じる力が弱まってしまうのです。
そうして、「自分の本音に気づけない」状態になり、抜け出せない理由の一つになってしまいます。
③ 恐れと罪悪感による“偽りの安定”
・「この関係を壊したら一人になってしまう…」
・「私がいなくなったらこの人は生きていけないのではないか」
・「NOと言ったら見捨てられるかも」
このような恐れや罪悪感が、関係を維持する“縛り”として働いてしまうのです。
表面的には“相手に尽くしている”ように見えるかもしれません。
しかし実際は、強い不安と孤独感を埋めるための行動であることが多く、その構造に気づかない限り繰り返してしまいます。
◆カウンセリングでできること
まず、カウンセリングで共依存や自己犠牲の相談を受けたとしても、別れることを勧めたりはしません。
今の関係性を見直し、共依存・自己犠牲からの回復を図ります。
そのためには、「思考パターン」「感情の扱い方」「関係性の築き方」の3方向からのサポートさせていただきます。
① 認知の書き換え(スキーマ・セラピーや認知行動療法ベース)
・「NO=悪いこと」「役に立たないとダメ」という思考のクセに気づき、それがどこから来たものなのか一緒に振り返ります。
・否定的な自己イメージを書き換えて、 「私は私でいていい」と思える土台を作っていきます。
サポート例:
- 過去の“信念”の棚卸しと見直し
- 今の人間関係における思い込みの再評価
- 自己肯定感の再構築ワーク
② 感情の言語化・抑圧解除
「本当は腹が立っていた」「本当は寂しかった」など、抑え込んできた感情を丁寧に言葉にしていく作業です。
感情にフタをするクセが強い人ほど、このステップが大切になります。
サポート例:
- 感情マップを使ったワーク
- セッション内での感情の実況トレーニング
- 「怒ってもいい」という体験の積み重ね
③ 境界線(バウンダリー)の確立
「相手の問題」と「自分の問題」を区別する練習をします。
健全な距離感や、依存しない関係性をつくるための“自他の境界線”を学びます。
サポート例:
- 断る練習、沈黙に耐える練習
- バウンダリーに関する図解ワーク
- 家族やパートナーとの“役割分担”の見直し
④ インナーチャイルドへのアプローチ
幼少期に感じていた「本当は甘えたかった」「守ってほしかった」気持ちを今の自分が受け止めてあげるセラピー的関わりです。
自分自身との関係性を修復する大切なステップです。
サポート例:
- 子どもの頃の体験を語るセッション
- 心の中の“傷ついた自分”に手紙を書くワーク
- 「今ならどう対応できる?」という再体験のワーク
⑤ 現実的な関係性の再構築
カウンセリングで気づいた自分軸をもとに、実際のパートナーシップや家族関係をどう整えていくかを一緒に考えます。
状況によっては、関係を続けるか・離れるかの判断もサポートします。
サポート例:
- 「支える」の線引きを整理する
- パートナーとの関係性の“再契約”
- 依存的な人からの心理的距離の取り方
共依存は“愛情のゆがんだ学習”の結果とも言えます。
たとえば、幼少期に「親の顔色を見て生きてきた」「自分の気持ちより、家族の都合を優先することが正解だった」など、安心と我慢が結びついた環境で育った場合、「自分の気持ちは後回しにするクセ」が当たり前になります。
その結果、大人になっても「NOと言うのは悪いこと」「役に立てない私は価値がない」という非合理的な信念を持ち続け、破綻した関係でも自ら離れることができなくなります。
◆まとめ:優しさと自己犠牲は違う
自己犠牲や共依存は、見た目は“優しさ”ですが、そこに自分の感情や境界がないと、ただの自己否定になってしまいます。
誰かのために生きる前に、まず「自分の気持ちを丁寧に扱うこと」が必要です。
カウンセリングは、あなたのままで価値があるという実感を育て直す、安全な場です。
もし今、「自分ばっかり我慢してる」と感じているなら、一度立ち止まり、一緒に“自分”を取り戻す作業を始めてみませんか?
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓