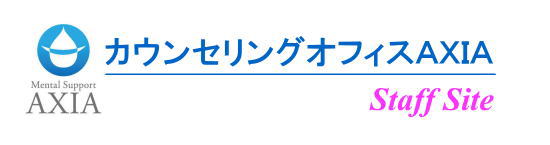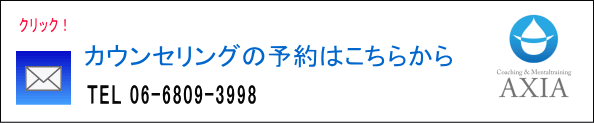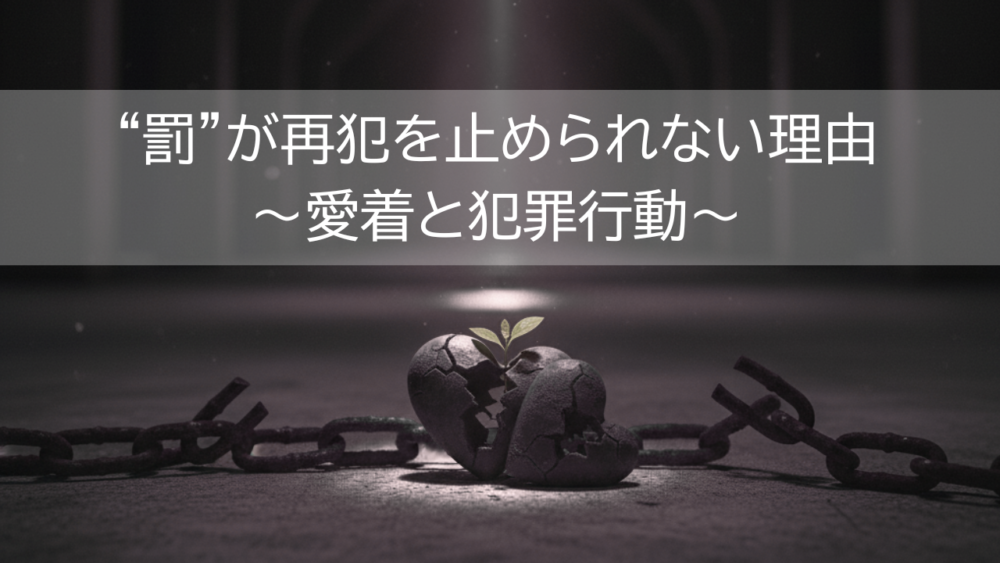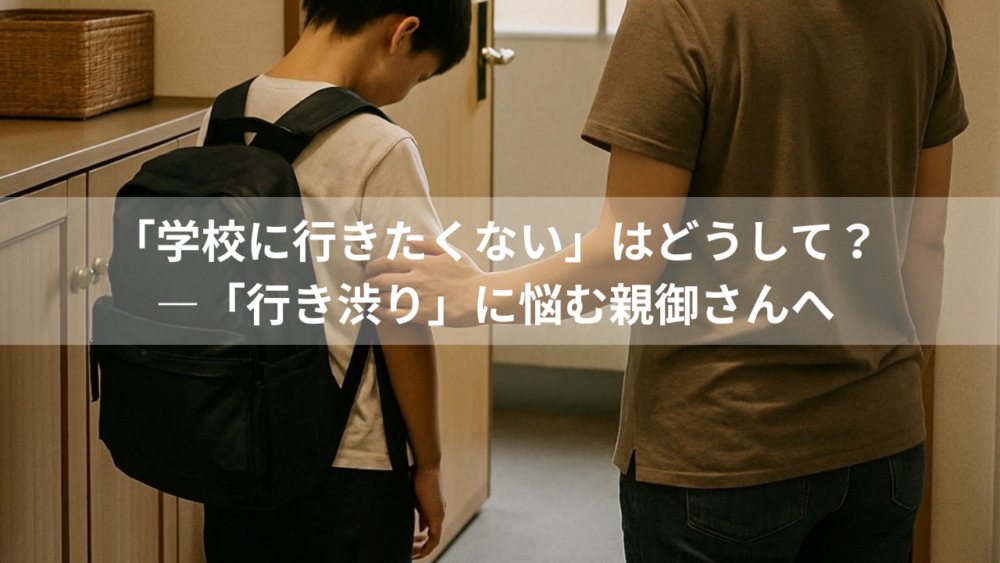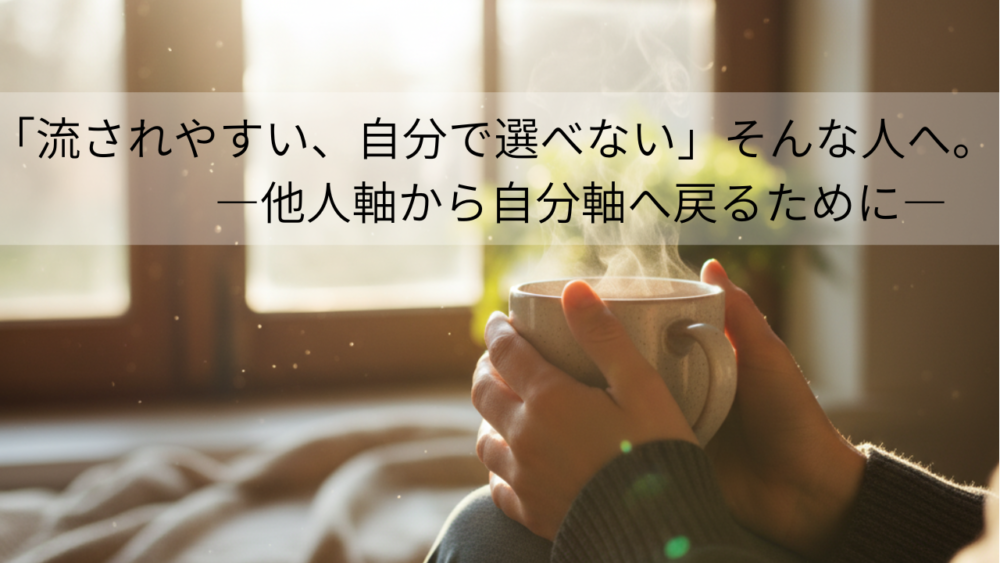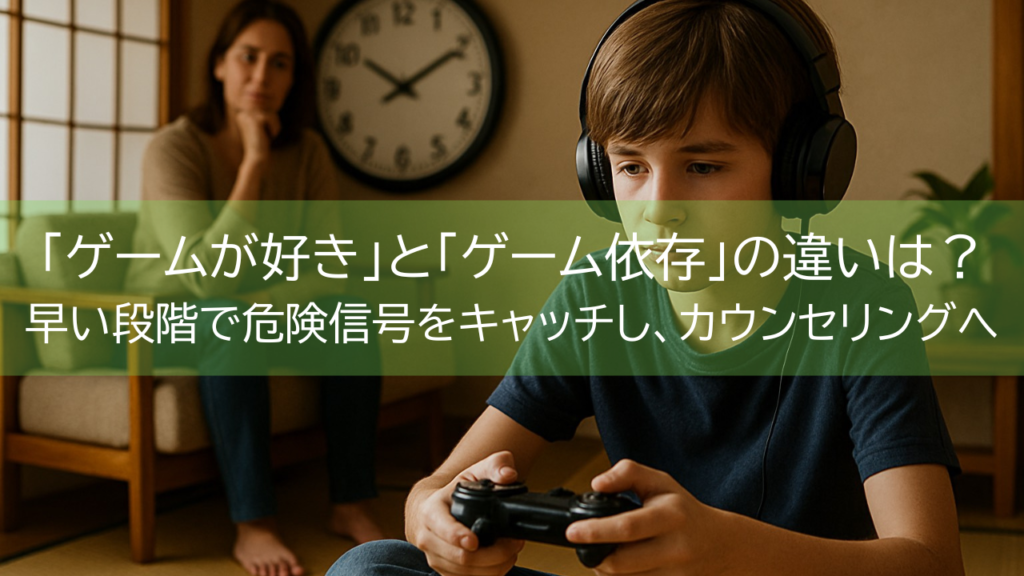
近年、スマホで無料ゲームアプリのクオリティがどんどん上がっていて今や誰もがプレイしています。
ゲームが好き、というだけなら、それは“趣味”の範囲かもしれません。
でも、
「ゲームに合わせたような生活スタイル」
「時間を決めても約束を守れない」
「取り上げると異常に怒る、暴れる」
そんな様子が見られるなら、少し立ち止まって考えてみる必要があります。
◆「ゲーム好き」と「ゲーム依存」は何が違う?
子どもたちがゲームに夢中になるのは自然なことでもあります。
ですが、“夢中”と“依存”には、大きな違いがあります。
- 夢中:好きで楽しんでいる。やめるときはやめられる。他のことにも興味がある。
- 依存:やめたくてもやめられない。ゲームが中心の生活。他のことが手につかない。
あなたのお子さんは「〇時まで」と言っていたのにやめなかったり、「やめて」と言うと怒り出したり無視したりしていませんか?
それは、もしかしたら“依存の初期サイン”かもしれません。
◆なぜ「やめられない」のか?
ゲームには、脳が心地よさを感じる仕組み(ドーパミンの分泌)があります。
レベルアップや報酬、仲間とのやりとりなど、子どもにとっては達成感や承認欲求を満たしてくれる場所になります。
それが“現実世界よりも快適”になってしまうと、自然とそちらにのめり込んでいきます。
しかも子どもは、まだ自分の欲求をコントロールする「自制心」が発達途中です。
「あとちょっとだけ…」が積み重なって、やめられなくなってしまうのです。
◆親が「叱っても変わらない」理由
「約束したでしょ!」
「何回言ったらわかるの?」
「もうゲーム取り上げるからね!」
こう言っても、なかなか行動が変わらないこと、ありませんか?
実は、“叱る”ことでは依存行動は改善しないことが多いのです。
むしろ、反発心を抱いたり、バレないようにしようという心理が働いてしまい、余計に意識がゲームに向いてしまいます。
さらに子どもは「どうせ分かってもらえない」と感じて、ゲームの世界に逃げ込んでしまうこともあります。
「叱る」よりも、「理解して関わる」ことがとても大切です。
◆危険信号を見逃さないために、親ができること
以下のような様子が見られたら、早めに対応してあげましょう。
- ゲーム時間が日ごとに延びている他の遊びや趣味に興味を持たなくなった
- 学校や友だちとの関係に支障が出ている
- ゲームができない日はイライラしたり落ち込んだりする
睡眠や食事のリズムが乱れている
こうした兆しは、「ちょっとした困りごと」のように見えて、実は心の中にあるストレスや不安のサインなのです。
◆「親の関わり方」が未来を変える
子どものゲーム依存には、親の関わり方が大きく影響します。
でもそれは、決して「親が悪い」ということではありません。
「どうしたらいいかわからない」「毎日怒ってばかりでしんどい」
そんな悩みを一人で抱え込まず、ぜひ専門家に相談してみてください。
カウンセリングでは、
- お子さんの状況の整理
- ご家庭での関わり方の工夫
- 親御さん自身のストレスケア
などを取り組んでいきます。
「まだ早いかな?」と思っても、「何か変かも…」と感じたそのときが、相談のタイミングです。
依存の加速はどんどん速度を上げていきます。
気づいたときにはどっぷり依存に…なんてなってしまわないよう対策が必要です。
◆最後に:大切なのは“問題を責める”のではなく、“理解する”こと
子どもがゲームにのめり込む背景には、日常のストレスや寂しさ、成功体験の少なさなど、様々な“心の事情”が隠れています。
表面的な行動だけを見て叱るのではなく、「なんでやめられないんだろう?」と、背景にある気持ちを知ってみることが大切です。
そのために、大人ができることはたくさんあります。
まだ成長の途中であるお子さんのこれからを一緒に考えていきましょう。
もし今、少しでも「確かにうちの子、気になるな…」と感じたら、お気軽にご相談ください。
ご予約・お問い合わせは下記バナーをクリック↓